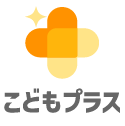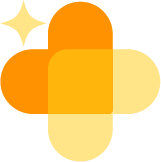1.中学生・高校生向けの放課後等デイサービスの必要性
放課後等デイサービスの対象は、小学生〜高校生の障がいを持つ児童です。しかし実際の利用者は小学生が多数を占めています。
厚生労働省の「放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書」(令和2年3月みずほ情報総研株式会社 注1)を参照すると、令和元年6月の1ヶ月間における年齢別の実利用者数の平均値は、小学生18.34人、中学生5.15人、高校生等が4.20人です。
受給者証は変わらず発行されるにもかかわらず、中高生の利用者数はあわせても小学生の半分程度です。これには以下の理由が考えられます。
- 学校生活が忙しくなり、平日の利用時間が確保しにくい
- 中高生向けのプログラムを提供する施設が少ない
中高生の放課後等デイサービス需要はあります。市場ニーズがあるにもかかわらず、そのニーズにビジネスチャンスを見出し、魅力的なカリキュラムを提供する施設数が少数なのです。
1-1.中高生向け放課後等デイサービスに求められる支援内容
放課後等デイサービスで中高生の利用者に求められるのは、将来の自立や就労に繋がるカリキュラムです。
一例として・・・
<自立支援>
- 公共交通機関などを使った自主登所
- 献立作りからの調理レク
- 洗濯物の干し、たたみ
<就労支援>
- VRを使ったSST(ソーシャルスキルトレーニング)
- 梱包作業(広報資料を封筒に入れる等)
- タイピングの練習から名刺作り
が挙げられます。
近年、放課後等デイサービスの市場は厳しくなってきています。
赤字施設の割合が37.4%あると、『利益率30%以上!放課後等デイサービスで儲かっている会社の特徴』でもお伝えしたとおり、今までと同じやり方では経営が難しい状況です。
したがって、今から放課後等デイサービスのフランチャイズ事業を始めるなら、中高生に向けたプログラムを検討されることをおすすめします。
ほかの教室が保有していない独自のコンテンツを、利用ニーズの高い中高生に届けることで、このビジネスで成功する確率が高まります。
1-1-1.こどもプラスの事例
こどもプラスでは、一人ひとりの苦手な分野や課題に寄り添った自立支援、VRを活用したSSTを中心に、プログラミングやパソコン操作など中高生の将来に繋がるプログラムを多数保有しています。
とくにSSTは擬似的な就労体験や反復練習など、VRならではの特長を生かしたコンテンツです。
魅力あるサービスを提供することで、子ども達の継続利用を促進し、中高生向けのコンテンツを持たない事業所からの移行も喚起します。
さらに就労支援事業を始めるための下準備にもなり、新たな事業展開にも繋がります。
この記事でも、弊社の保有する中高生向けコンテンツの魅力と、経営上の高い価値について詳しくお伝えします。幅広い年齢をカバーするこどもプラスの強みを実感していただけます。
2.中高生向けの放課後等デイサービスで提供したいカリキュラムとは

放課後等デイサービス(以下、放デイ)を中学生・高校生に利用してもらうためには、小学生とは別に就労を意識したプログラムが必要です。
心身の発達に重点を置く小学生とは違い、社会性やスキルの獲得など将来に結びつく療育内容に変えなければなりません。
2-1.障害児通所支援への中学生・高校生のニーズ
厚生労働省の「障害児通所支援の現状等について」(注2)に「通常の学級に在籍する発達障がいの可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒」の割合が掲載されています。
それによると、小学校全体での推定値が7.5%、中学校全体では4.0%です。学年が上がるごとに数値は下がりますが、中学3年生でも3.2%の生徒が「特別な教育的支援」を必要としているのです。
過去の調査になりますが、高校生のデータもあります。
厚生労働省が平成21年に調査した「高等学校における発達障害等困難のある生徒の状況」(注3)を参照すると、全日制高校の1.8%、定時制・通信制高校の15%前後の生徒が発達障がいを持っています。(※)
定時制・通信制高校の生徒を中心に、放デイの支援への需要は確実にあるのです。
2-1-1.社会で生きる基盤の確立が求めらている
適切な支援を行わないと、高校卒業後に自立や就労で苦労します。
厚生労働省が平成30年に発表した「子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン」(注4)に「18歳到達後の児童養護施設入所者の現在の課題」の調査結果では。
- 基本的生活の確立、社会生活スキルが十分でない・・・45.4%
- 本人の自立に関する不安等が大きい・・・39.5%
と、自立と就労にかかわる2項目が解決すべき課題の上位に挙がっているのです。中高生のうちにトレーニングをしっかりと行い、社会で生きるための基盤をつくる必要があります。
支援の効果は、厚生労働省の「障害者の就労支援対策の状況」(注5)に明示されています。
就労移行支援や就労継続支援(詳しくは後述)をとおして一般就労に成功した人の数は、年々増え続け、令和元年には平成15年の17倍に達しています。
需要の高まりを受けて、こどもプラスでは自立支援・就労支援のための多彩なプログラムを用意し、一人ひとりを支援します。こどもプラスの保有するプログラムには以下の特長があります。
- 職業体験をとおし、興味や適性を発見できる
- 面接や電話応対練習、マナー講習などで、社会生活の基盤を育成する
- 就労につながるパソコンスキルを獲得する
これらを適性や苦手にしている点に着目しながら提供します。子ども達は自分自身の将来像をつくり、自立と就労を具体的に意識して取り組むようになります。
以下でコンテンツの中身を具体的に説明します。
※「発達障害教育推進センター」によると、発達障がいの児童生徒数は毎年約6,000人ずつ増加しています。割合の数値も上がっていることが予想されます。
参考:発達障害教育推進センター「統計情報」 注6
2-2.小学生と中高生で行うべき療育内容は異なる
心身の発達を促すため、こどもプラスでは運動療育を主軸に、一人ひとりの個性に応じた療育を小学生の利用者には提供しています。楽しく取り組める運動遊びがプログラムの中心です。
中高生に対しては運動療育を提供しながらも、自分の興味や適性への気づきを促し自立を促進すると共に、将来の進学や就労へ向けた具体的な訓練も行います。
自立支援
自立支援では、自主通所の練習や公共交通機関への乗り方など移動にかかわることや、絵画や音楽、料理の体験など適性を見つけるためのさまざまなプログラムを行います。
とくに自主通所には力を入れています。自分の力で自由に動けることは、自立への第一歩だからです。
就労支援
就労支援では、SST(ソーシャルスキルトレーニング)を導入しています。SSTは対人関係や基本的な社会生活の技能を習得する訓練です。一般的な放デイで実施するには、以下の問題が生じます。
- 電話応対や名刺交換など限られた場面しか設定できない
- 職員は福祉の専門家ばかりで、一般企業で何が必要か分からない
- 教えるべきことの幅が広すぎて、療育の焦点が絞れない
多くの放デイでは、就労支援の教えるべきポイントが絞れず、継続したSSTを行うことができていません。保護者が求めている療育が提供できず、中途半端に終わってしまうことが多々あります。
こどもプラスのSSTは、その点で強みを発揮します。なぜなら、保護者が求めている声を集めて、リクエストにあったコンテンツを開発しているからです。
グループ会社のRYD株式会社と協力をして、VR技術を使ったサービスを開発・提供しています。
VRならば通勤訓練や職業体験など、外に出なければできないことも教室内で疑似体験できます。繰り返し体験をすることによって、納得いくまで練習可能です。
効果的なSSTを利用することで、こどもプラスの教室には中高生比率が100%、つまり中高生に特化した形で運営している教室もあります。
弊社と同じように、保護者のご要望をもとに開発をしている事業者はほとんどありません。今後もニーズに基づき、さらに良質なコンテンツを新しく開発していきます。
フランチャイズ加盟者様からはロイヤリティを頂く分、それ以上に価値のあるコンテンツ開発力を実感して頂けます。
2-3.就学に繋がるパソコンスキルや職場での社会性の獲得
こどもプラスでは一人ひとりの自立や就労を支えるための多彩なトレーニングを実施しています。
就労や就学に向けた個別のパソコントレーニング
パソコントレーニングは目的に応じて個別に行います。
一般企業への就職を希望する場合、まずはタイピングの練習から入り、名刺の入力作業、書類の作成と段階的にステップアップします。この練習でビジネス書類の作成がスムーズに行えるようになります。
専門学校への進学や、専門スキルの獲得を目指す子どもには、進路や目標に応じたスキルトレーニングを提供します。
- プログラミング
- Webデザイン
- 現代アート
- ドローン
- 写真加工
- Amazonでの販売技術の獲得
などが例です。
ほかにも幅広い取り組みを実施しています。この理由は、必ずしも利用者が「やりたいこと」と「向いている」ことが一致するわけではないからです。
また保護者が「やらせたいこと」と子ども達の希望が合致するわけではありません。「やりたいことがわからない」人も多くいます。
実際に「カフェで働きたい」という子どもに「お菓子づくり」を体験してもらったら、すぐに飽きてしまったという事例もあります。
だからこそ、関連会社と協力しながら新しいコンテンツを開発し、利用者には多岐にわたる体験をしてもらっているのです。
子ども達が得意な分野を伸ばし、将来の仕事に活かせるように、さらには人生における生きがいを見つけられるように、私たちは一人ひとりの夢や目標を全力で応援します。
社会体験・外出訓練の実施
社会性を獲得し自立を促進するため、実際に外出して行う訓練も実施しています。商業施設の使用、公共交通機関の利用などです。障がいを持った子ども達は、あまり買い物に出かける機会がありません。
そのため・・・
「お金の概念が身につかない」
「電車やバスの乗り方や切符・ICカード乗車券の買い方が分からない」
「お店のレジで購入・会計する流れを知らない」
など、日常生活を送るうえでの問題を抱えていることがあります。こどもプラスでは学校休業日を活用し、積極的に外出し社会体験の機会をつくります。
この訓練を行うことで、子ども達は社会の仕組みを学び、自分と社会とのかかわりを実感します。
2-4.親も気付かなかったさまざまな療育コンテンツで得意や好きを発見
放デイに通う子にはさまざまな個性があります。これから社会で生きていくために、中学生・高校生は自分と向き合い、好きなことや適性を見つけることは大切です。
こどもプラスでは個性を伸ばすコンテンツを用意し、好きなことや将来の夢を見つける手助けを行っています。以下コンテンツ開発の参考にしてみてください。
絵が得意な子にはタブレットで創作活動を、数学が得意な子にはプログラミングの体験を、料理が好きな子にはお菓子作りや石鹸作りの体験など、一人ひとりの長所を重点的に伸ばします。
以下は提供しているコンテンツの例です。
- DTMなどのソフトを使って楽曲を制作する
- Scratchなどのソフトを使ってプログラミングをし、ゲームを作る
- Amazonで商品を売れるよう、写真のアップロードや加工方法を学ぶ
- 材料を用意するところからお菓子作りを始め、お店ごっこで模擬販売まで行う
- キャンドルや石鹸を作り、オンライン販売のスキルを習得する
これらの体験をとおし、子ども達は適性を見つけ、楽しみながら自分の将来と向き合います。家庭や学校では気づけないことも、こどもプラスのプログラムなら見つかるのです。
3.中高生向けの独自カリキュラムが多数あります

放課後等デイサービスの「こどもプラス」が、中学生・高校生の療育に強いと評価を頂いています。理由は、独自のカリキュラムを多数持ち、その一つひとつが効果的だからです。
弊社の取り組みを具体的に説明しながら、中高生向けのコンテンツが、事業展開にもたらす可能性をお話しします。
私たちの教室には、未就学児を対象とした児童発達支援のころからお預かりし、10年以上通所している生徒もいます。
幼少時から就労まで面倒を見られるのは、子どもの成長を身近で見守れるため、職員にとっても大きな喜びです。
子ども達は主体的に楽しんでプログラムに参加するため、長期にわたり利用を継続します。継続利用は、事業所に安定した収益ももたらします。
就労支援の形態が確立されれば、放デイとは別に就労支援事業を始めることが可能です。新しい事業を運営することで、法人全体の利益を高められます。
3-1.VRを活用した疑似体験で就労につながるスキルが身につく
こどもプラスのSSTは、放デイのために設計された独自のVRシステムです。
一番の特徴は、臨場感のある中で反復練習することができる点です。さまざまな場面を当事者の視点で体験しながら、一つひとつを着実に身につけられます。
主な提供内容は以下のとおりです。
- 通勤・通学の練習
- 面接の練習
- 職業体験
- 電話応対練習
VRシステムには「Realize」というアプリを利用します。イメージ動画として、こちらをご覧ください。
疑似体験のトレーニングを継続的に行うことで、子ども達は徐々に社会性を身に付けます。
コミュニケーションの仕方を理解し、親の会話や表情から気持ちを汲み取ろうとするなど、保護者にも実感できる変化が現れます。
子ども達も自分の成長を実感して喜び、たとえ学校生活が忙しくても進んで通所しようとします。
3-2.就労支援事業を始めるための下準備にもなる
こどもプラスでは中高生の利用者増加にあわせ、新たに就労支援型放課後等デイサービス「夢を叶える就労トレーニング教室」(運営:RYD株式会社)も展開しています。
さらに放デイとは別に、就労支援事業も展開できます。
就労支援事業には「就労移行支援事業」「就労継続支援事業」「就労定着支援事業」があり、概要は以下のとおりです。(厚生労働省 「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」参照 注7)
就労移行支援事業
一般就労を希望する障がいを持った人に対し、知識・能力の向上や、実習、職場探しなどの支援を行う事業です。
事業所は地域障害者職業センターと連携し、基礎訓練、実践的訓練を提供すると共に、通所後期にはハローワークと連携し、求職活動支援を行います。
厚生労働省の「就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について」(注8)を参照すると、令和2年4月時点での事業所数は3,001件で、平成29年の3,357件を境に減少に転じています。
令和元年10月から基本報酬が、利用者の「就職後6ヶ月以上定着率」で算定されるようになり、各事業所の支援効果が試されるようになりました。
1ヶ月の売上を試算します。
1単位の単価10円の地域で、1日20人の利用者、月22日の営業を想定します。
- 就職後6か月以上定着率5割以上:1094単位
- 福祉専門職員配置等加算(常勤職員の35%以上):15単位
- 就労支援関係研修終了加算:6単位
- 食事提供体制加算:30単位
- 送迎加算:21単位
一日一人あたり合計:1166単位
1166単位×10円(単価)×20人×22日=5,130,400円
就労継続支援事業
障がいを持ち、一般企業で働くことが困難な人たちを対象に、就労機会を与える事業です。
事業者と雇用契約を結ぶ「A型」と非雇用型の「B型」があります。多くの就労機会が確保できるよう、利用定員は10人からです。
厚生労働省の「平成 30 年 社会福祉施設等調査の概況」(注9)によると、事業所数はA型が3,839件で前年比1.7%の増加率、B型は11,835件で前年比7.2%の増加率です。
基本報酬は利用者の平均工賃月額により決定されます。
B型の1ヶ月の売上を試算します。
1単位の単価10円の地域で、職員の人員配置7.5:1以上、1日20人の利用者、月22日の営業を想定します。
・平均工賃月額45,000円以上:702単位
・就労移行支援体制加算:42単位
・利用者負担上限額管理加算:150単位
・福祉専門職員配置等加算(常勤職員の35%以上):15単位
・食事提供体制加算:30単位
・送迎加算:21単位
*一日一人あたり合計:960単位
960単位×10円(単価)×20人×22日=4,224,000円
(参照:厚生労働省「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」 注10)
就労定着支援事業
就労移行支援、就労継続支援などを経て一般就労へ移行した障がい者に対し、日常生活や社会生活で問題が生じないか確認する事業です。利用者の自宅や企業等を訪問し、対面で支援を行います。
平成30年10月から施行された新しい事業のため、事業所数は毎月増加し、令和2年4月時点で1,228件にのぼります。(厚生労働省「就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について」参照)
あわせて利用者数も増え続けており、今後の拡大が予想されます。就労定着率により基本報酬が決定されるため、就労移行支援事業同様、実績が重要視されます。
1ヶ月の売上を試算します。
1単位の単価10円の地域で、利用者数20人を想定します。
・就労定着率9割以上:3215単位/月
・職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算:120単位/月
・企業連携等調整特別加算:240単位/月
*ひと月一人あたり合計:3575単位
3575単位×10円(単価)×20人=715,000円
放デイからの事業展開を考えると、就労移行支援事業が最も取り組みやすいでしょう。今ある就労支援コンテンツを利用・改良しながら事業展開できます。
例えば、こどもプラスのある教室で行っている中高生向けプログラムの一部に、
- 社会性:ビジネス用語を学ぶ
- 自己理解:おもしろプロフィールを書く
- 意思表示:先生の話を聞く
- 感情のコントロール:顔のパーツを使って遊ぶ
などがあります。
豊富なコンテンツを用意しておくことで、今後の事業展開に役立ちます。
3-3.放デイだけではなく就労支援までの長い事業モデルを提供します
就労支援事業までカバーできれば、幼少期から大人まで一貫した支援ができます。
なお、トータルサポートを行う事業所は、多機能型事務所とも呼ばれています。多機能型事務所は、『放課後等デイサービスを多機能型事業所にするメリット・デメリット』で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
就労継続支援事業で就労機会の提供を行えば、放デイの卒業生の選択肢にもなります。
こどもプラスは中高生向けの充実したプログラムがあるため、どの教室でも多くの生徒が継続利用します。
この先、就労支援事業の展開も行い、子ども達が大人になった後も一貫したサービスを提供したいと考えています。
4.中高生向け放デイの新規・継続売上をあげる方法

利用人数や提供したサービスに応じて国保連から給付金が出る仕組みは、小学生でも中高生でも変わりません。
しかし、多くの放デイは中高生の利用が少ないため、小学校卒業時点で退所者が出て、その人数分の給付金を得られなくなり減収となります。
その一方で中高生向けの魅力的なコンテンツを保有する教室は、生徒を一極集中させられる可能性があります。
小学生向けの放デイから利用者が移行してくるからです。さらに就労支援の専門性をアピールできれば、障がい児向けの塾のように新規利用者を開拓できます。
経営の安定には生徒の通所日を増やすことも重要です。短時間でも「行きたい!」「参加したい!」と思える支援ならば、子ども達は自ら時間をつくり通所します。
ここからは、こどもプラスの事例をもとに、中高生向け放デイの運営上のメリットを説明します。
4-1.既存教室からの移行で法人全体で退所人数を減らせる
先にご紹介した放デイの年齢別実利用者数平均値を鑑みると、「預かり+α」として捉えられている放デイの場合、中学校に進学をすれば利用者は通う理由がなくなります。
小学校を卒業した子ども達が「通いたい」と思える放デイにするためには将来に役立つ療育が必要です。
それには中高生専門の教室をつくり、サービスや人員を集約させることが効率的です。提供するコンテンツの質や専門性を高め、その評判を広めることができればブランディング面でも優位に立てます。
小学校を卒業する退所希望者に、中高生専門教室への移行案内を行えば、法人全体の利用者数を維持できます。
ただし、そのためには小学校高学年からVRを体験してもらうなど、専門教室へ移行することへの抵抗をなくすことと、保護者への周知徹底が必要です。
4-2.中高生専門以外の放デイから新規利用の獲得が見込める
中高生向けの放デイを展開する場合、ほかの放デイの利用者も潜在顧客として候補に挙げられます。すでに利用している教室から、どうすれば移行してもらえるのでしょうか。
ポイントになるのは療育の専門性です。中学生は部活動や課外活動が盛んなため、預かり目的で放デイを探すことは多くありません。
就労支援や個性の伸長など、明確な目的を持っているため、専門性の高さが利用者や保護者から選ばれるポイントになります。
こどもプラスは就労や就学へのニーズを満たすプログラムで実績があることから、ほかの教室では満たせないニーズに応えられます。
放デイをはじめて利用する中高生を集客することは簡単でありません。しかし、すでに教室に通所しており、かつ現状に不満がある人を対象にすることで、円滑に新規利用者の獲得ができます。
実際にこどもプラスの教室には、ほかの小学生向け放デイから移行してきた生徒も多数通所しています。
4-3.利用児童と保護者が満足することで継続利用に繋がり安定的な収益となる
中高生の場合、利用者が満足しなければ継続利用はありません。それには、一人ひとりの個性を大切にし、それを伸ばすプログラムが必要です。
子どもが楽しく通所し、目に見える成長を見せれば、親も放デイを高く評価します。
こどもプラスは、利用者や保護者からいただく意見を大切にし、教室運営の改善やプログラムの改良・開発を行っています。
保護者の声を取り入れた改善事例
例えば、以前ある保護者から「お金の支払の練習を行ってほしい」との声がありました。
レジでの支払方法を教えたくても、支払に時間をかければお店の迷惑となってしまうため、日常ではなかなかできずにいたのです。
私たちはすぐに外出訓練に反映し、教室での練習の後にお店の協力を得て実践練習を行いました。子ども達は成功体験を積み、保護者からは感謝の言葉をいただきました。
利用者の声を取り入れた改善事例
利用者の要望を聞き、それを伸ばすトレーニングで感謝されたこともあります。料理に強い興味を示す子に対し、夏休みを利用して献立の作成から料理レクチャーまでを毎日繰り返し行いました。
その子はあっという間に料理の腕を上げ、著しい成長に保護者も大変喜んでくれました。
これらはこどもプラスだからこそ生まれた事例です。利用者や保護者の声を聞くことはできても、それを反映したコンテンツの開発まで可能な放デイはほかにありません。
VRやオンライン技術をはじめ、さまざまなコンテンツをつくり続けてきたこどもプラスだからこそ、成し得ることです。ほかの放デイができないことを実現できれば、自ずと選ばれる教室になります。
私たちはこのように利用者や保護者のニーズに応え、満足度を上げ信頼を得てきました。
多忙な中高生の場合、利用日数の確保や継続利用は難しいテーマですが、こどもプラスは需要を満たし、信頼を勝ち取ることで、安定的な収益を得ています。
さいごに

中高生の集客は多くの放デイで苦労するテーマです。だからこそ、魅力的なコンテンツを提供できる放デイは一人勝ちする可能性があります。
こどもプラスではVR技術を利用したSSTと自立支援を中心に据え、パソコントレーニングや社会性獲得のための外出訓練など、社会に出てから長く役立つプログラムで、一人ひとりの利用者に寄り添います。
個別のトレーニングは高い効果を発揮し、利用児童や保護者から喜ばれます。
中高生向けのコンテンツの充実は、各教室に以下の恩恵をもたらします。
・ほかの放デイから利用者が移行してくる
・利用者が満足とやる気を得ることで、利用日数が増える
・就労まで継続的な通所をしてもらえる
私たちはこのように利用者や保護者のニーズに応え、満足度を上げ信頼を得てきました。
多忙な中高生の場合、利用日数の確保や継続利用は難しいテーマですが、こどもプラスは需要を満たし、信頼を勝ち取ることで、安定的な収益を得ています。
より詳しいノウハウや運営のコツは個別面談やフリーダイヤルでご説明いたします。少しでも興味を持たれた方は、お気軽に「問い合わせページ」よりご連絡ください。
<参考文献>
注1)厚生労働省 令和元年度障害者総合福祉推進事業「放課後等デイサービス実態把握及び質に関する調査研究報告書」 令和2年3月 みずほ情報総研株式会社
注3)厚生労働省 「高等学校における発達障害等困難のある生徒の状況」
注4)厚生労働省 「子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン」
注7)厚生労働省 「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
注8)厚生労働省 「厚生労働省の「就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について」