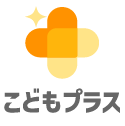放課後等デイサービス経営者の年収について多くの方が関心を持っており、障害者施設経営の年収と合わせて検討される方も増えています。
福祉事業への参入を考える際、経営者として得られる年収は重要な判断材料の一つです。
本記事では、放課後等デイサービス経営者の年収の実態から、障害者施設経営の年収向上のポイントまで、FC加盟を検討される方に向けて詳しく解説していきます。
放課後等デイサービス経営者の年収の実態と障害者施設経営の現状
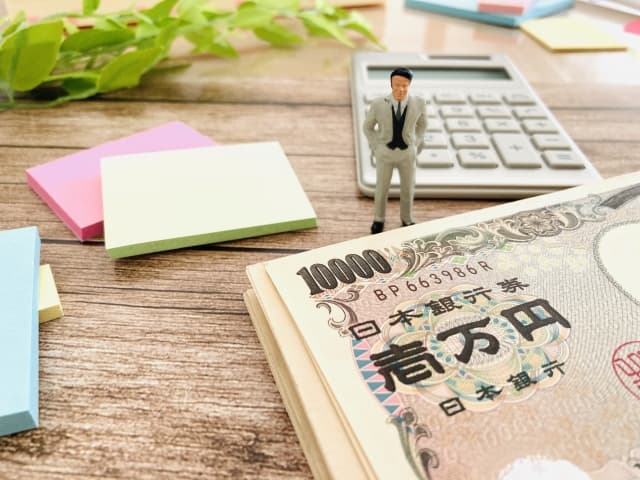
放課後等デイサービス経営者の年収は平均393万円で、障害者施設経営の年収水準と比較すると特徴的な傾向があります。
福祉事業への参入を検討する経営者にとって、実際の年収水準を把握することは重要な判断材料となります。
放課後等デイサービス経営者の年収について、公的なデータと業界の実情を踏まえながら詳しく見ていきましょう。
障害者施設経営の年収全体の中での位置づけも含めて解説します。
厚生労働省データによる年収実態
厚生労働省が公表する「平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果」によると、放課後等デイサービスの施設長・管理者の平均年収は393万円となっています。
この数値は平成28年度の年間所得を基にしたもので、業界全体の実態を示す重要な指標です。
(参照:平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果 | 厚生労働省)
同調査によると、障害福祉サービス全体の施設長・管理者の平均年収は521万円となっており、放課後等デイサービスは約130万円ほど低い水準にあります。
また、資本金2,000万円未満の企業役員の平均年収567万円と比較しても、放課後等デイサービス経営者の年収は控えめな水準と言えるでしょう。
年収格差の背景にある事業特性
放課後等デイサービス経営者の年収が他の障害者施設経営と比較して低い理由には、事業の特性が大きく関係しています。
放課後等デイサービスは児童福祉法により一日の定員が制限されており、多くの施設で最大10名となっています。
この人数制限により、一ヶ月の売上はおよそ300万円が上限となり、学習塾のように利用者を増やして収益を拡大することが困難です。
売上に限界があることで、経営者の年収にも影響が出ているのが現状です。
赤字施設と黒字施設の年収格差
独立行政法人福祉医療機構のレポートによると、令和3年時点で放課後等デイサービスの赤字施設割合は45%となっており、約半数が収支で苦戦しています。
(参照:2021年度(令和3年度)児童系障害福祉サービスの経営状況について | 独立行政法人福祉医療機構)
赤字施設の経営者と黒字施設の経営者では、当然ながら年収に大きな差が生まれます。
平均年収393万円は全体の数値であり、成功している施設の経営者はこれを大きく上回る年収を得ています。
逆に、利用者確保に苦戦している施設では、経営者の年収も低くなる傾向があります。
障害者施設経営における年収の安定性
放課後等デイサービス経営者の年収の特徴として、安定性の高さがあげられます。
収入の約9割が国民健康保険団体連合会(国保連)からの給付費であるため、利用代金の未収金や売掛金回収に悩まされることはありません。
また、景気変動に左右されにくく、世帯年収890万円以下の家庭では月額4,600円の上限があるため、経済状況が悪化しても利用者の離脱が起こりにくい構造になっています。
一度利用者を獲得できれば、小学1年生から高校3年生まで最大12年間の長期利用が期待できます。
放課後等デイサービス経営者の年収は393万円が平均で、障害者施設経営の年収としては安定性が高い一方、事業特性により上限があることが特徴です。
次に、放課後等デイサービス経営者の年収を向上させるための具体的な収益構造について解説します。
放課後等デイサービス経営者の年収向上につながる障害者施設の収益モデル

放課後等デイサービス経営者の年収を上げるには、障害者施設経営の年収の仕組みである給付費制度を理解し、収益を最大化することが重要です。
放課後等デイサービスの収益構造は独特で、この仕組みを理解することが経営者の年収向上の第一歩となります。
給付費の計算方法から加算の取得まで、収益を最大化するポイントを詳しく解説していきます。
給付費による収益計算の基本
放課後等デイサービスの収益は「単位制」で計算されます。
一日の収益は以下の計算式で決定されます。
- 「一日児童一人あたりの単位数」×「地域単価(10円〜)」×「利用人数」
地域単価は地域の人件費格差を考慮して設定されており、最高は東京23区の12円、政令市や中核市などの大規模自治体ほど高い傾向にあります。
この計算式から分かるように、利用人数を定員に近づけることが収益向上の基本となります。
基本報酬と加算報酬の内訳
児童一人あたりの単位数は、基本報酬と加算報酬で構成されます。
2023年現在の基本報酬は以下の通りです。
基本報酬
- 平日:604単位
- 学校休業日:721単位
この基本報酬に、以下のような加算報酬を組み合わせることで収益を向上させます。
主要な加算報酬
- 児童指導員等加配加算:最大187単位(保育士等の配置)
- 専門的支援加算:最大187単位(理学療法士等の配置)
- 送迎加算:往復108単位
これらの加算を適切に取得することで、児童一人あたりの単価を大幅に向上させることができます。
月間売上の計算例
具体的な収益シミュレーションを見てみましょう。
定員10名、地域単価10円の施設で、主要な加算を取得した場合:
加算込みの単位数
- 平日:604+187+108=899単位(8,990円/人)
- 学校休業日:721+187+108=1,016単位(10,160円/人)
月間売上(平日22日、休業日8日の場合)
- 平日売上:8,990円×10人×22日=1,977,800円
- 休業日売上:10,160円×10人×8日=812,800円
- 月間合計:約279万円
この例では約280万円の月間売上となり、年間では3,350万円程度の売上が見込めます。
加算取得による収益向上策
放課後等デイサービス経営者の年収を向上させるには、以下の加算を効果的に取得することが重要です。
定期的に取得できる加算
- ・児童指導員等加配加算(日常的な人員配置で取得)
- ・送迎加算(送迎サービス提供時)
- ・専門的支援加算(専門職配置時)
実施時に取得できる加算
- ・家庭連携加算:1回187単位(家庭訪問実施時)
- ・事業所内相談支援加算:1回100単位(施設内面談実施時)
- ・関係機関連携加算Ⅰ:1回200単位(学校等との連携時)
これらの加算を漏れなく取得することで、月間数万円から十数万円の収益向上が期待できます。
利用者確保の重要性
収益計算式からも明らかなように、利用人数の確保が収益の基盤となります。
定員10名の施設で毎日8名程度の利用者を確保できれば、安定した収益基盤を築くことができます。
利用者確保のポイントは以下の通りです。
- ・地域のニーズに合った専門的なプログラムの提供
- ・保護者との信頼関係構築
- ・学校や相談支援事業所との連携強化
- ・口コミによる評判向上
放課後等デイサービス経営者の年収向上には、障害者施設経営の年収の仕組みを理解し、給付費の最大化と利用者確保が不可欠です。
続いて、放課後等デイサービス経営者の年収を制限する要因と、それを克服する障害者施設経営の戦略について解説します。
放課後等デイサービス経営者の年収を制限する要因と障害者施設経営の課題

放課後等デイサービス経営者の年収には制約があり、障害者施設経営の年収向上には競争激化と規制の制限を理解することが重要です。
放課後等デイサービス業界が直面している課題は、経営者の年収に直接的な影響を与えています。
市場環境の変化と法的制約を理解することで、より効果的な経営戦略を立てることができるでしょう。
売上上限による年収制約
放課後等デイサービスの最大の特徴は、法的に定められた定員制限です。
児童福祉法により一日の受け入れ人数が制限されており、多くの施設で最大10名となっています。
この制限により、月間売上は約300万円が上限となり、学習塾のように利用者を増やして売上を伸ばすことができません。
年間売上が3,600万円程度に制限される中で、人件費や家賃などの固定費を差し引くと、経営者の年収にも自ずと上限が生まれてしまいます。
この構造的な制約が、放課後等デイサービス経営者の年収が他業種と比較して低くなる主な要因となっています。
競争激化による利用者確保の困難
厚生労働省の「障害児通所支援の現状等について」によると、放課後等デイサービス事業所数は急激に増加しており、令和5年時点で全国約20,000カ所を超える施設が存在しています。
事業所数の急増により利用者の獲得競争が激化し、特に都市部では事業所が密集している状況です。
新規開設しても思うように利用者が集まらず、定員を満たせない施設が増加しています。
利用者数の不足は直接的に売上減少につながり、経営者の年収にも大きな影響を与えています。
人件費率の高さによる収益圧迫
独立行政法人福祉医療機構の調査によると、放課後等デイサービスの人件費率は非常に高く、赤字施設では売上の93.7%に達しています。黒字施設でも67%と高い水準にあります。
(参照:2021年度(令和3年度)児童系障害福祉サービスの経営状況について | 独立行政法人福祉医療機構)
福祉事業の特性上、有資格者の配置が必要で人件費が高くなりがちです。
また、こどもの安全確保のために手厚い職員配置が求められることも、人件費率上昇の要因となっています。
高い人件費率は経営者の取り分を圧迫し、年収向上の阻害要因となっています。
報酬改定による収益変動リスク
3年に一度実施される報酬改定は、放課後等デイサービス経営者の年収に大きな影響を与えます。
令和3年の報酬改定では、基本報酬の見直しと新たな加算の創設が行われましたが、すべての施設にとって有利な変更ではありませんでした。
改定により取得できなくなった加算がある施設では、月間数十万円の収益減少となり、経営者の年収にも直接的な影響が出ています。
給付費に依存する事業特性上、行政の方針変更が経営に与える影響は避けられない課題となっています。
専門性確保の困難さ
近年の報酬改定では「専門性」がより重視される傾向にあります。
理学療法士や作業療法士などの専門職員を配置することで高い加算を取得できますが、これらの人材確保は容易ではありません。
専門職員の採用には以下の課題があります。
- 高い人件費による収益圧迫
- 専門職の慢性的な人材不足
- 小規模施設での採用の困難さ
- 地方での人材確保の難しさ
専門性を高めることで収益向上は期待できますが、それに伴うコスト増加が経営者の年収向上を阻む場合も多いのが現実です。
地域格差による収益差
地域単価の差により、同じサービスを提供しても地域によって収益に大きな差が生まれます。
東京23区の12円と地方の10円では、同じ利用者数でも月間約50万円の収益差となります。
この地域格差は以下の影響をもたらします。
- ・都市部と地方での経営環境の格差
- ・専門職員確保の地域差
- ・利用者密度の違いによる集客難易度の差
規制遵守によるコスト増加
児童福祉法に基づく厳格な運営基準の遵守は、以下のコストを発生させます。
- ・定期的な職員研修費用
- ・安全管理体制の整備費用
- ・記録・報告業務の人件費
- ・施設・設備の維持管理費
これらの必要経費は、表面的な売上に現れない部分で経営を圧迫し、結果として経営者の年収を制限する要因となっています。
放課後等デイサービス経営者の年収は構造的な制約と競争激化により制限されがちですが、障害者施設経営の年収向上には戦略的なアプローチが必要です。
最後に、放課後等デイサービス経営者の年収を最大化する障害者施設経営の成功戦略について解説します。
放課後等デイサービス経営者の年収を最大化する障害者施設経営の成功戦略
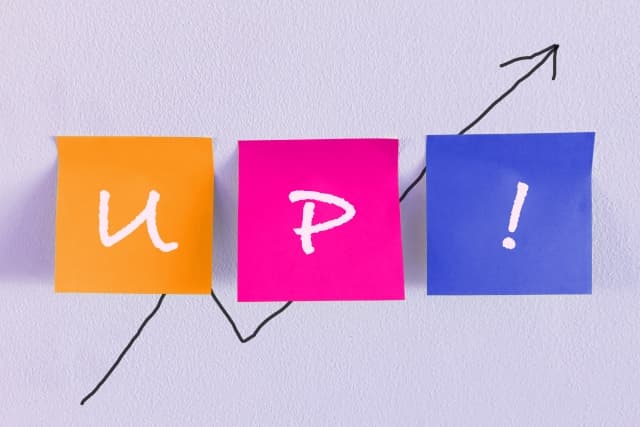
放課後等デイサービス経営者の年収を最大化するには、障害者施設経営の年収の限界を突破する革新的な経営戦略が必要です。
従来の単一施設運営では年収の上限が決まってしまうため、収益を最大化し経営者の年収を向上させるには、新しいアプローチが求められます。
成功している事業者の戦略を参考に、具体的な年収向上の方法を解説していきます。
中高生特化による競争回避戦略
みずほ情報総研の調査によると、放課後等デイサービスの年齢別実利用者数は小学生18.34人に対し、中学生5.15人、高校生4.20人となっており、中高生市場は競争が相対的に緩やかです。
(参照:放課後等デイサービス実態把握及び質に関する調査研究報告書 | みずほ情報総研株式会社)
多くの事業所が小学生をターゲットとする中で、中高生に特化することで以下のメリットがあります。
中高生特化のメリット
- 競合施設が少なく利用者確保が容易
- 自立支援・就労支援により高い付加価値を提供
- 保護者のニーズが高い将来に向けた支援を実現
- 専門性の高いサービスによる差別化
中高生向けのプログラムとして、以下のような内容が効果的です。
- ・就労移行支援を見据えたビジネスマナー指導
- ・IT関連スキル(プログラミング・タブレット操作)の習得
- ・生活自立に向けた実践的な訓練
- ・進路相談や将来設計のサポート
多店舗展開による年収倍増戦略
単一施設の売上上限を克服する最も効果的な方法が多店舗展開です。
1店舗あたり年間約3,600万円の売上上限があっても、3店舗展開すれば約1億円の売上となり、経営者の年収も大幅な向上が期待できます。
多店舗展開のメリット
- 店舗数に比例した売上・利益の拡大
- 地域でのブランド認知度向上
- 利用者の受け入れ枠拡大による社会貢献
- 職員のキャリアパス創出
成功する多店舗展開のポイント
- ・1店舗目の安定経営を確立してからの展開
- ・地域ニーズに応じた店舗コンセプトの差別化
- ・効率的な管理体制の構築
- ・人材育成システムの整備
多店舗展開では、児童発達支援、小学生向け、中高生向けなど、年齢や専門性で店舗を区分することで、それぞれの特色を明確にできます。
実費事業導入による収益の多角化
給付費の上限を突破する画期的な方法が、教室の空き時間を活用した実費事業の導入です。
許認可事業と実費事業を組み合わせることで、施設の稼働率を最大化し、売上の上限を取り払うことができます。
実費事業の具体例
学習塾・習い事教室の運営
- ・放課後等デイサービス終了後の夜間時間帯を活用
- ・発達障害に特化した学習指導
- ・既存の備品・設備の有効活用
- ・放課後等デイサービス利用者の継続利用
専門プログラムの提供
- ・プログラミング教室
- ・ドローン操縦教室
- ・アート・音楽療法
- ・運動療育プログラム
これらの実費事業により、月間50万円〜100万円の追加収益を得ることが可能で、年収に直接反映されます。
FC加盟による経営効率化と年収向上
独立開業と比較して、FC加盟には以下の年収向上につながるメリットがあります。
開業リスクの軽減
- ・実績のあるビジネスモデルの活用
- ・開業時期の短縮による早期収益化
- ・適切な立地選定による集客力向上
運営効率の改善
- ・標準化されたオペレーションによる人件費削減
- ・効果的な加算取得ノウハウの提供
- ・継続的な経営指導による収益最大化
コンテンツ・ノウハウの提供
- ・専門的な療育プログラムの利用
- ・最新の報酬改定情報の共有
- ・実費事業導入のサポート
年収向上の具体的な数値目標
成功している放課後等デイサービス経営者の年収向上プロセスは以下のようになります:
| 段階 | 店舗数 | 年間売上 | 経営者年収目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 1店舗 | 3,600万円 | 500万円〜700万円 |
| 第2段階 | 2店舗 | 7,200万円 | 800万円〜1,200万円 |
| 第3段階 | 3店舗 | 1億800万円 | 1,200万円〜2,000万円 |
| 第4段階 | 実費事業込み | 1億5,000万円+ | 2,000万円〜 |
長期的な資産形成戦略
放課後等デイサービス経営者の年収を最大化するには、短期的な収入向上だけでなく、長期的な資産形成も重要です。
事業価値の向上
- 安定した利用者基盤の構築
- 専門性の高いサービス体制の確立
- 地域での確固たるブランド地位の確立
投資・運用の活用
- 事業キャッシュフローの効率的な再投資
- 不動産投資による資産形成
- 関連事業への投資拡大
放課後等デイサービス経営者の年収は戦略的なアプローチにより大幅な向上が可能で、障害者施設経営の年収として十分に魅力的な水準を実現できます。
放課後等デイサービス経営者の年収は、適切な戦略と継続的な努力により大きく向上させることができます。
平均393万円という数値に留まることなく、多店舗展開や実費事業の導入により年収1,000万円以上の実現も十分に可能です。
福祉事業でありながら安定した収益基盤を持つ放課後等デイサービスは、長期的な資産形成の観点からも魅力的な事業と言えるでしょう。
障害者施設経営の年収として、社会貢献と経済的成功の両立を図ることができる数少ない分野の一つです。
経営者として成功するためには、業界の特性を理解し、競争に打ち勝つ差別化戦略が不可欠です。
FC加盟により実績のあるノウハウを活用することで、より確実な年収向上への道筋を描くことができるでしょう。