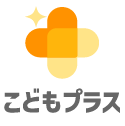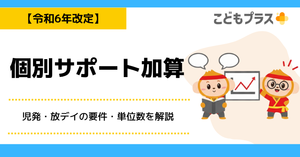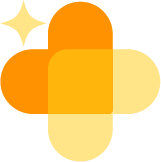個別サポート加算とは? 令和6年改定の概要
個別サポート加算は、大きく分けて以下の3つのニーズに対応する加算です。
- ケアニーズの高い児童(行動上の課題、著しく重度の障害など)
- 要保護・要支援児童
- 不登校の状態にある児童
令和6年度の改定では、特に(Ⅰ)において強度行動障害に関する研修修了者の配置が評価されるようになり、(Ⅱ)では関係機関との連携頻度が強化、(Ⅲ)として不登校児童への学校・家庭との連携支援が新設された点が大きなポイントです。
個別サポート加算(Ⅰ)の単位数と算定要件(放デイ)
個別サポート加算(Ⅰ)は、ケアニーズの高い児童、または著しく重度の障害を有する児童への支援を評価するものです。
【放デイにおける加算(Ⅰ)の単位数】
| 対象児童 | 単位数 |
| (1) ケアニーズの高い児童 | 90単位/日 |
| (1) のうち強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が支援した場合 | 上記に+30単位/日
(合計120単位/日) |
| (2) 著しく重度の障害を有する児童 | 120単位/日 |
算定要件
ケアニーズの高い児童(90単位 + 30単位)
- 要件: 「就学児サポート調査表」の点数合計が13点以上の児童にサービスを提供すること。
- 追加要件(+30単位): 上記に加え、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が当該児童への支援を行うこと。
著しく重度の障害を有する児童(120単位)
- 要件: 「就学児サポート調査表」の項目(食事、排せつ、入浴、移動)のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする児童にサービスを提供すること。
留意点
- 加算(Ⅰ)の(1)と(2)は併算定できません。
- +30単位の加算(基礎研修修了者による支援)は、強度行動障害児支援加算を算定している場合は算定できません。
- ただし、強度行動障害児支援加算を算定している場合でも、加算(Ⅰ)の基本部分(90単位または120単位)は併算定可能です(Q&A VOL.2 問7)。
- 主として重症心身障害児を通わせる事業所(重身型)の基本報酬を算定している場合は対象外です。
【参考】児童発達支援(児発)との違い 児童発達支援における加算(Ⅰ)は、今回の改定で基本報酬に包括化されました。そのため、児発で加算(Ⅰ)が算定できるのは「著しく重度の障害児」(重症心身障害児や各種手帳1・2級所持者など)に限定されており、放デイとは要件が大きく異なります。
個別サポート加算(Ⅱ)の単位数と算定要件
加算(Ⅱ)は、児童相談所やこども家庭センター等との連携が必要な「要保護児童」または「要支援児童」への支援を評価します。
算定要件
- 児童相談所、こども家庭センター、要保護児童対策地域協議会、または医師(以下「連携先機関等」)と連携し、支援を行うこと。
- あらかじめ保護者の同意を得て、通所支援計画に位置づけること。
- 連携先機関等との情報共有(児童の状況等)を6ヶ月に1回以上行い、その記録を文書で保管すること。(※改定前は「年1回以上」でした)
-
留意点
- 加算(Ⅱ)を算定する場合、同じ観点での連携について関係機関連携加算(Ⅲ)は算定できません。
- 保管する「文書」は、双方で共有している必要があり、事業所のメモ書きのみでは認められません。
個別サポート加算(Ⅲ)の単位数と算定要件【新設】
加算(Ⅲ)は、令和6年度に新設された区分で、「不登校の状態にある児童」に対して、学校や家庭と緊密に連携して支援を行った場合を評価します。
算定要件
- 対象: 「不登校の状態にある児童」(※)
- あらかじめ保護者の同意を得て、通所支援計画に位置づけること。
- 通所支援計画の作成にあたり、学校と連携すること。
- 学校との情報共有(対面・オンライン可)を月に1回以上行い、要点を記録し、学校側にも共有すること。
- 家族への相談援助(個別)を月に1回以上行い、要点を記録すること。
(※)「不登校の状態にある児童」とは? 「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く。)」と定義されています。
留意点
- 加算(Ⅲ)算定のために行った学校連携について、関係機関連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)は算定できません。
- 加算(Ⅲ)算定のために行った家族への相談援助について、家族支援加算(Ⅰ)は算定できません。
個別サポート加算に関するQ&A(公式資料より)
Q. 加算(Ⅲ)の「不登校の状態」は、事業所が判断すればよいか?
A. 事業所が不登校の状態にあると考えた児童について、保護者の同意を得た上で、学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で「緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要」と判断された場合に支援を進めます。 また、月1回以上の学校との情報共有の際に、不登校の状態について確認し、支援の継続が必要か否かを学校と検討することとされています。 (出典:Q&A VOL.1 問49)
Q. 加算(Ⅰ)の「基礎研修修了者による加算(+30単位)」は、強度行動障害児支援加算と併算定できるか?
A. 算定不可です。 なお、個別サポート加算(Ⅰ)の基本部分(ケアニーズの高い児童:90単位、著しく重度の障害児:120単位)自体は、強度行動障害児支援加算と併せて算定可能です。 (出典:Q&A VOL.2 問7)
個別サポート加算 算定に向けたポイントと参考文献
個別サポート加算を適切に算定するためには、以下の体制整備と記録が不可欠です。
加算(Ⅰ)
「就学児サポート調査表」を正しく評価・運用する体制。
加算(+30単位)を目指す場合、職員の「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)」の受講を計画的に進める。
加算(Ⅱ)
児童相談所やこども家庭センター等と「6ヶ月に1回」情報共有を行う定期的な連携フローを確立し、必ず共有文書を残す。
加算(Ⅲ)
「月1回」の学校との情報共有と、「月1回」の家族への個別相談援助の両方を確実に実施し、記録する。
参考文献
本記事の作成にあたり、以下の公的資料を参照しています。