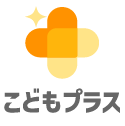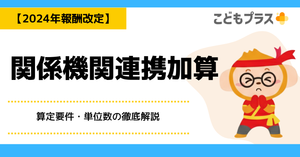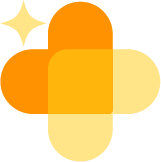関係機関連携加算とは?(2024年度改定のポイント)
関係機関連携加算は、放課後等デイサービス事業所が、児童の通う学校や児童相談所、医療機関などの関係者と連携し、会議の開催や情報共有を行うことで、児童への理解を深め、支援の質を高める取り組みを評価する加算です。
2024年度の報酬改定では、従来の学校等との連携(I)(II)に加え、以下が大きなポイントとなりました。
関係機関連携加算(III)の新設
児童相談所、こども家庭センター、医療機関、保健所等との情報連携(会議)が評価対象になりました。
関係機関連携加算(IV)の新設
児童の就職先(一般企業や官公庁等)との連絡調整や相談援助が評価対象になりました。
これにより、個別支援計画の作成時以外でも、日常的な情報連携が評価されるようになり、より多角的な支援体制の構築が促されています。
関係機関連携加算の単位数(区分一覧)
各区分の単位数と概要は以下の通りです。
| 区分 | 単位数 | 概要(連携先と内容) |
| 関係機関連携加算(I) | 250単位/回
(月1回限度) |
学校等と**「通所支援計画の作成・見直し」**のための会議 |
| 関係機関連携加算(II) | 200単位/回
(月1回限度) |
学校等と**「児童の情報共有」**のための会議((I)以外) |
| 関係機関連携加算(III) | 150単位/回
(月1回限度) |
児相・医療機関等と**「児童の情報共有」**のための会議 |
| 関係機関連携加算(IV) | 200単位/回
(1回限度) |
就職先(企業等)との連絡調整・相談援助 |
関係機関連携加算(I)の算定要件
(I)は、計画作成のために学校等と連携する、最も基本的な加算です。
連携先
児童が日常的に通う学校、保育所、認定こども園、児童発達支援センター等
連携内容
「通所支援計画の作成または見直し」に関する会議の開催
主な要件:
- あらかじめ保護者の同意を得ること。
- 学校等と会議を開催すること(テレビ電話装置等(オンライン)の活用も可能)。
- 会議で共有された情報を踏まえ、通所支援計画を作成または見直しを行うこと。
- 会議の出席者、日時、内容の要旨、計画への反映内容等を記録すること。
- 日頃から学校等との日常的な連絡調整に努めること。
関係機関連携加算(II)の算定要件
(II)は、(I)の計画作成・見直し「以外」で、日常的な情報共有のために学校等と連携した場合に算定します。
連携先
学校、保育所、認定こども園、児童発達支援センター等
連携内容
児童の心身の状況や生活環境等の「情報共有」のための会議の開催、または会議への参加
主な要件:
- あらかじめ保護者の同意を得ること。
- 学校等と情報共有の会議を開催、または学校等が開催する会議に参加すること(オンライン可)。
- 会議の出席者、日時、内容の要旨等を記録すること。
- 会議の結果を踏まえ、必要に応じて通所支援計画の見直し等を行うこと。
関係機関連携加算(III)の算定要件
2024年度に新設された(III)は、児相や医療機関との連携を評価します。
連携先
児童相談所、こども家庭センター、医療機関、保健所、保健センター等
連携内容
児童の心身の状況や生活環境等の「情報共有」のための会議の開催、または会議への参加
主な要件:
- あらかじめ保護者の同意を得ること。
- 児相や医療機関等と情報共有の会議を開催、またはこれらの機関が開催する会議に参加すること(オンライン可)。
- 会議の出席者、日時、内容の要旨等を記録すること。
- 会議の結果を踏まえ、必要に応じて通所支援計画の見直し等を行うこと。
- 注意点:
- 個別サポート加算(II)(要保護・要支援児童への支援)を算定している場合、その加算の要件として求められる児相等との情報連携については、(III)を算定できません。
関係機関連携加算(IV)の算定要件
同じく新設された(IV)は、児童の「就職」に焦点を当てた連携を評価します。
連携先
就学児が就職する企業、官公庁等
※ 就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業所は対象外です。
連携内容
就職先への連絡調整、および相談援助
主な要件:
- あらかじめ保護者の同意を得ること。
- 就職先に対し、児童の状態や事業所での支援方法等を記録した文書を渡すこと。
- 就職先との連絡調整や相談援助を行った場合、その相手や内容を記録すること。
関係機関連携加算の主なQ&A(算定の注意点)
算定にあたり、特に注意が必要な点をQ&A形式でまとめます。
Q1. 電話だけの情報交換でも算定できますか?
A1. 算定できません。
(I)~(III)は、会議の開催または参加による情報連携が必須です。電話は、あくまで日常的な連絡調整の手段であり、会議の代わりとはなりません。
Q2. (I)(II)(III)は同じ月にまとめて算定できますか?
A2. 併算定にはルールがあります。
(I)と(II)の併算定は不可
同じ「学校等」との連携であるため、同一月はどちらか1回のみ算定可能です。
(I)と(III)の併算定は可能
(例:学校と計画見直しの会議(I)を行い、別日に病院と情報共有会議(III)を行った場合)
(II)と(III)の併算定は可能
(例:学校と情報共有会議(II)を行い、別日に児相と情報共有会議(III)を行った場合)
【最重要注意点】ただし、(I)または(II)の会議と、(III)の会議の参加者が同一の場合(例:学校との情報共有会議に、医療機関の担当者も同席したケース)は、一度の会議で(II)と(III)の両方を算定することはできません。
Q3. 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議への参加で(II)は算定できますか?
A3. 算定できません。
サービス担当者会議への協力は、指定基準(運営基準第15条)で定められた事業者の責務であり、本加算の評価対象とはなりません。
Q4. 地域の課題を話し合う会議(事例検討会など)への参加でも算定できますか?
A4. 算定できません。
本加算は、加算対象となる「当該児童」についての具体的な情報共有や連絡調整を評価するものです。地域の課題検討のために一事例として取り上げるような会議は対象外です。
まとめ
2024年度の報酬改定により、関係機関連携加算は、学校だけでなく医療機関や就職先まで連携対象が広がり、より柔軟な連携が評価されるようになりました。
- (I):学校等と計画作成の会議
- (II):学校等と情報共有の会議
- (III):児相・医療機関等と情報共有の会議
- (IV):就職先との連絡調整
算定には「会議の開催(オンライン可)」「内容の記録」が必須であり、「電話のみ」や「サービス担当者会議」では算定できない点に注意が必要です。特に(I)と(II)の併算定不可ルールを正しく理解し、適切な連携体制の構築と確実な記録管理を行いましょう。
【公的資料】参考文献
本記事の作成にあたり、以下の公的資料を参照しています。解釈や申請に関する詳細は、必ず最新の原文および管轄の自治体にご確認ください。
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要」(令和6年4月1日)
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日)
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2」(令和6年4月12日)