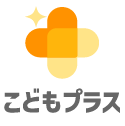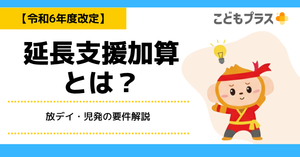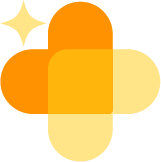延長支援加算の概要と令和6年度改定のポイント
延長支援加算は、基本報酬で定められた時間区分(※)を超える支援の提供を評価するものです。
児童発達支援(児発)
- 5時間を超える支援
放課後等デイサービス(放デイ)
- 平日(授業終了後):3時間を超える支援
- 学校休業日:5時間を超える支援
【令和6年度改定の主なポイント】
- 預かりニーズへの明確な対応:従来の「支援時間」の区分(例:放デイ平日3時間)を超える長時間の支援について、「預かりニーズに対応した延長支援」として明確に評価されるようになりました。
- 職員配置の見直し:延長支援時間帯の安全を確保するため、職員2名以上の配置が必須となりました。このうち1名は、児童発達支援管理責任者(児発管)を含む、人員基準で定められた職員(児童指導員や保育士など)であることが求められます。
- 医療的ケア児への対応:医療的ケア児に対して延長支援を行う場合は、安全確保のため看護職員等の配置(または連携体制の確保)が要件化されました。
延長支援加算の算定要件(必須チェックリスト)
延長支援加算を算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 基本時間を超える支援の実施
- 上記の「基本の時間(児発5時間、放デイ平日3時間・休業日5時間)」を超える時間帯に、計画に基づいた支援を提供すること。
② 計画・同意・理由の明確化
- 通所支援計画(個別支援計画)に、延長支援の必要性や内容、時間帯をあらかじめ位置づけておくこと。
- 保護者の事前同意を得ていること。
- 保育所等の一般施策で受け入れが困難など、やむを得ない理由がある旨が**障害児支援利用計画(相談支援事業所が作成)**に記載されていること。
③ 職員の配置
- 延長支援を提供する時間帯に、職員を2名以上配置すること。
- (うち1名は、児発管、児童指導員、保育士など人員基準上の職員であること)。
- (利用者が10名を超える場合は、10名またはその端数を増すごとに1名追加配置が必要)。
④ 医療的ケア児への体制
- 医療的ケア児に延長支援を行う場合、看護職員を1名以上配置するか、医療機関等との連携により必要なケアを提供できる体制を確保すること。
⑤ 記録の実施
- 実際に延長支援を提供した日時と時間を正確に記録すること。
⑥ その他のルール
- 延長支援の時間に送迎時間は含まれません。
- 利用者の都合で計画より時間が短くなった場合でも、30分以上の支援があれば「30分以上1時間未満」の区分で算定が可能です。
延長支援加算の単位数(一覧表)
延長支援の時間に応じて、以下の単位数が1日あたり加算されます。
(※児発・放デイ共通、令和6年度改定対応)
| 支援時間 | 障害児(重身・医ケア児を除く) | 重症心身障害児(重身) または 医療的ケア児 |
| 30分以上1時間未満 | 61単位 | 128単位 |
| 1時間以上2時間未満 | 92単位 | 192単位 |
| 2時間以上 | 123単位 | 256単位 |
- 注1:「30分以上1時間未満」は、原則として計画が1時間以上であったものの、利用者都合等で短くなった場合に算定可能です。
- 注2: 重症心身障害児(重身)を主として受け入れる事業所の場合、単位数や要件が一部異なる場合があります。
延長支援加算の算定額シミュレーション
実際に延長支援加算を取得した場合の算定額例を見てみましょう。
(※地域区分を「10円」として計算した場合の一例です)
【例】放課後等デイサービス(平日)で、Aさんに1時間半の延長支援を月5回実施した場合
- 該当単位数: 1時間半→ 「1時間以上2時間未満」の区分に該当→ 92単位(Aさんが重身・医ケア児でない場合)
- 月間の合計単位数:→ 92単位 × 5日 = 460単位
- 月間の算定額:→ 460単位 × 10円(地域区分) = 4,600円
延長支援加算のQ&A(よくある質問)
厚生労働省から示されているQ&Aに基づき、実務で迷いやすい点を紹介します。
Q1. 利用者都合で、基本の支援時間(例:放デイ平日3時間)が短くなりました。その後の延長支援(計画通り)は算定できますか?
A1. 算定できます。
基本報酬は「計画上の時間」で算定可能です。そのため、基本時間が利用者都合で短くなっても、延長支援は「計画上の基本時間を超えた時間」として、実際に行った時間に基づき算定できます。
(出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 問1)
Q2. 延長支援(例:朝9時~10時)の途中で体調不良になり、基本支援(10時~)を受けずに帰宅しました。延長支援加算は算定できますか?
A2. 算定できません。
延長支援加算は、あくまで「基本報酬が算定されること」を前提としています。このケースでは基本支援が行われていないため、延長支援加算も算定できません。
(ただし、連絡調整等を行った場合は「欠席時対応加算」の対象となる場合があります)
(出典:同上 Q&A VOL.3 問2)
Q3. 事業所の「営業時間」外でも延長支援加算は算定できますか?(例:営業時間は9時~16時だが、8時~9時に延長支援を行った)
A3. 算定できます。
延長支援加算は、運営規程上の「営業時間」ではなく、基本報酬の算定対象となる「基本の時間(児発5時間、放デイ平日3時間・休業日5時間)」を超えるかどうかで判断します。
(出典:同上 Q&A VOL.3 問3)
Q4. 基本支援の前(例:1時間)と後(例:1時間)の両方で延長支援を行いました。合計2時間分(123単位)で算定しますか? それとも1時間分(92単位)×2回で算定しますか?
A4. 1日の合計時間(この場合は2時間)で算定します。
延長支援時間は1日分を合計して、該当する区分(この場合は「2時間以上」)の123単位を算定します。
(出典:同上 Q&A VOL.3 問4)
Q5. 医療的ケア児の延長支援時、看護職員は延長時間中ずっと配置が必要ですか?
A5. 常に配置することまで求めるものではありません。
ただし、医療的ケア児に対して安全に延長支援が行えるよう、必要な医療的ケアを「適時適切に提供できる体制」を確保する必要があります(例:医療機関との連携体制など)。
(出典:同上 Q&A VOL.6 問5, 問6)
延長支援加算の公的な引用・参考文献
本記事を作成するにあたり、以下の公的資料を参照しています。実務においては、必ず自治体(指定権者)の最新情報も併せてご確認ください。
- 厚生労働省: 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
- 厚生労働省: 「障害児通所支援・障害児入所施設等における報酬・基準について(令和6年度報酬改定)」
- 厚生労働省: 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 (令和6年5月2日)」
- 厚生労働省: 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.6 (令和6年7月1日)」