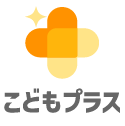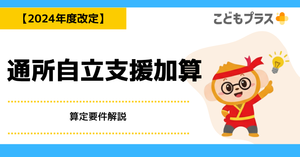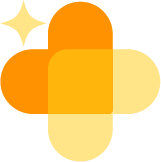通所自立支援加算とは?(2024年度新設)
通所自立支援加算は、学校・居宅等と事業所間の移動について、児童が自立して通所できるようになることを目指し、職員が同行して計画的に支援を行った場合に算定できる加算です。
単なる「送迎」とは異なり、公共交通機関の利用方法や安全な横断歩道の渡り方などを具体的に教え、自立を促す「支援」であることが重要です。
通所自立支援加算の単位数
通所自立支援加算の算定要件(対象児童・支援内容)
算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 対象となる児童
公共交通機関や単独での移動経験が乏しく、一人での通所に不安がある児童。
- 通所自立支援によって、自立した通所が見込まれる児童。
(注)重症心身障害児は対象外となります。
2. 支援内容
- 児童が公共交通機関を利用、または徒歩で通所する際に、従業者が同行すること。
- 自立した通所に必要な知識(移動経路、公共交通機関の利用方法、乗車マナー、緊急時の対応方法など)を習得するための助言や援助を行うこと。
3. アセスメントの実施
- 安全な通所を確保するため、事前に十分なアセスメントを行うこと。
- 児童の状態や特性(特に医療的ケアを要する児童の場合は、医療濃度や移動時間等も)を考慮し、支援の実施を判断すること。
通所自立支援加算 算定のためのプロセスと体制
算定要件に加え、適切なプロセスと体制の構築が求められます。
1. 計画と同意
- あらかじめ児童本人と保護者の意向を確認し、保護者の同意を得ること。
- 支援内容、個別の配慮事項、安全確保策などを通所支援計画に明記し、計画に基づいて支援を行うこと。
2. 支援体制
- 児童1人に対し、従業者1人が個別支援を行うのが基本です。
(ただし、児童の状態に応じ、安全が確保される場合は児童2人に対し従業者1人でも可)
- 医療的ケアを要する児童に支援を行う場合は、看護職員等の医療的ケアを行える職員が同行する必要があります。
3. 安全確保と連携
- 支援の安全確保に関する事項を安全計画に位置づけ、職員に周知すること。
- 支援にあたる従業者への研修等を行うこと。
- 学校や公共交通機関等と連携を図り、地域理解の促進にも努めること。
4. 記録
- 支援を実施した日時、支援の具体的な状況、児童の様子、次回の留意点等を記録すること。
通所自立支援加算 Q&A(留意点)
実務で迷いやすいポイントをQ&A形式でまとめます。
Q1. 算定できる期間に上限はありますか?
A1. 支援開始から90日間を限度に算定可能です。 ただし、進学、進級、転居といった環境の変化により、改めて自立支援が必要と判断される場合は、再度アセスメントを行った上で算定が可能です。
Q2. どのくらいの距離から算定できますか? 「極めて近距離」とは?
A2. 同一敷地内の移動や、極めて近距離の移動は算定できません。 「極めて近距離」とは、例えば学校の目の前に事業所がある場合や、徒歩数分程度の距離を指します。途中に横断歩道があるといった理由だけでは、加算の対象とは考えにくいとされています。
Q3. 学校からバス停までは送迎バスで、バス停から事業所まで支援した場合も算定できますか?
A3. 可能です。 居宅や学校から事業所までの一部の区間(例:バス停から事業所)を支援する場合でも、それが固定された通所経路であれば算定対象となります。ただし、その区間が「極めて近距離」に該当しないことが前提です。
Q4. 職員(従業者)の交通費は保護者に請求できますか?
A4. できません。 同行する従業者の交通費(電車代やバス代)は事業所の負担となります。なお、児童本人の交通費については、利用者(保護者)側が負担します。
Q5. 自転車での通所を支援する場合も対象ですか?
A5. 可能です。 ただし、あくまで「自立した通所」に向けた支援(安全な自転車の乗り方、交通ルールの遵守など)が目的である必要があります。児童を自転車の後部座席に乗せて送迎するような、支援要素の乏しい形態は算定できません。
Q6. 支援に同行する職員に資格要件はありますか?
A6. 指定基準により置くべき従業者(児童指導員や保育士など)に限定はされていませんが、加算の趣旨に基づき、児童の状態や特性を踏まえて適切に通所自立支援を実施できる従業者を配置する必要があります。
Q7. 支援(同行)している時間は、サービス提供時間に含まれますか?
A7. 含まれません。 通所自立支援を行った時間(学校から事業所まで同行した時間など)は、放課後等デイサービスのサービス提供時間とは区別されます。
通所自立支援加算の参考文献
本加算に関する解釈や詳細は、厚生労働省から発出されている以下の資料で確認できます。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)
- 問44(極めて近距離の考え方、部分的な支援)
- 問45(職員の交通費)
- 問46(自転車での通所)
- 問47(同行する従業者)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2(令和6年4月12日)
- 問8(サービス提供時間)