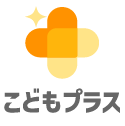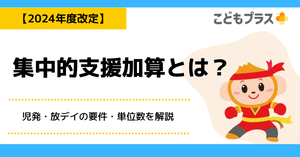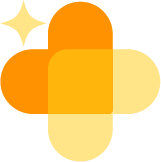集中的支援加算の概要【2024年度(令和6年度)新設】
まずは加算の全体像を把握しましょう。
目的
状態が悪化した強度行動障害児に対し、専門家(広域的支援人材)の助言のもと、事業所が集中的な支援(アセスメント、環境調整、支援計画の見直し等)を行い、児童の状態の安定と支援体制の再構築を図る。
対象事業所
- 対象事業所: 児童発達支援、放課後等デイサービス
単位数
- 単位数: 1000単位/回
算定上限
- 期間: 集中的支援を開始した日の属する月から3ヶ月以内
- 回数: 1月に4回まで
【重要】算定の前提
この加算を算定するには、事前に支給決定自治体(市町村)へ「集中的支援の実施依頼」の申請を行う必要があります。児童の状態悪化が見られた場合、まずは自治体へ相談することがスタートラインとなります。
集中的支援加算の対象となる児童(強度行動障害)
加算の対象となるのは、以下の「強度行動障害児支援加算確認票」のスコア合計が『20点以上』であり、かつ市町村が支援の必要性を認めた児童です。
強度行動障害児支援加算確認票(簡易版) 行動障害の各項目について、見られる頻度に応じた点数を合計します。
| 行動障害の内容 | 月に1回以上 (1点) |
週に1回以上 (3点) |
ほぼ毎日・1日に頻回等 (5点) |
|---|---|---|---|
| 1. ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりする | 1点 | 3点 | 5点 |
| 2. ひどく叩いたり蹴ったりする | 1点 | 3点 | 5点 |
| 3. 激しいこだわり | 1点 | 3点 | 5点 |
| 4. 激しい器物破損 | 1点 | 3点 | 5点 |
| 5. 睡眠障害 | 1点 | 3点 | 5点 |
| 6. 食べられないものを口に入れる等の食事に関する行動 | 1点 | 3点 | 5点 |
| 7. 排せつに関する強度の障害 | 1点 | 3点 | 5点 |
| 8. 著しい多動 | 1点 | 3点 | 5点 |
| 9. 通常と違う声を上げたり、大声を出す | – | – | 5点 |
| 10. 沈静化が困難なパニック | – | – | 5点 |
| 11. 他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為 | – | – | 5点 |
| 合計 | 20点以上 |
注:正確なスコア判定は、厚生労働省の定める正式な確認票に基づき行ってください。
集中的支援加算の算定要件と流れ
加算を算定するには、自治体への申請後、広域的支援人材と連携して一連のプロセスを踏む必要があります。
算定までの流れ(フロー)
- 発生・相談: 対象児童の状態が悪化。事業所または保護者が自治体に相談。
- 申請: 事業所が自治体に対し「集中的支援」の実施依頼を申請。
- 連携: 自治体が広域的支援人材の派遣等を調整。
- アセスメント: 広域的支援人材が事業所を訪問(またはオンライン)し、児童・事業所のアセスメントを実施。
- 計画作成: 広域的支援人材と事業所が共同で「集中的支援実施計画」を作成。
- 同意: 事業所は保護者に対し、計画内容を説明し同意を得る。
- 支援実施: 計画に基づき、広域的支援人材の助言・援助を受けながら事業所が支援を実施。
- 見直し: 計画は概ね1ヶ月に1回以上の頻度で見直す。
- 加算算定: 広域的支援人材から助言援助等を受けた日(アセスメント含む)に算定(月4回まで)。
算定要件のポイント
- 広域的支援人材の関与: 訪問またはオンラインで、広域的支援人材によるアセスメントや助言・援助を受けること。
- 集中的支援実施計画の作成: アセスメントに基づき、状態改善のための環境調整や支援内容を盛り込んだ計画を共同で作成し、定期的に見直すこと。
- 計画に基づく支援の実施: 広域的支援人材の助言を受けながら、事業所の従業者が支援を行うこと。
- 他事業所との連携: 対象児童が他の障害児通所支援事業所を利用している場合、当該事業所と連携すること。
- 記録と同意: 支援内容を記録し、実施について保護者の同意を得ること。
集中的支援加算における「広域的支援人材」とは?
本加算の鍵となる「広域的支援人材」とは、強度行動障害に関する高度な専門性を持ち、都道府県等によって選定された人材を指します。
具体的には、以下のいずれかに該当する者です。
- 中核的人材養成研修の講師等(ディレクター・トレーナー)である者
- 発達障害者支援体制整備事業による発達障害者支援地域支援マネジャーである者
- その他、強度行動障害を有する児者への支援に知見を有すると都道府県等が認める者
事業所が独自に探すというよりは、自治体への申請を通じて調整・派遣されるケースが中心となると想定されます。
集中的支援加算に関するQ&A
報酬改定に関する公式Q&Aから、特に重要な点を抜粋します。
Q. 集中的支援加算の算定期間(3ヶ月)終了後、再度、算定することは可能か。
A. 期間内に終了することが必要である。ただし、何らかの事情により、その後も再び集中的支援の必要がある場合には、再度、必要な手続き(自治体への申請等)を踏まえて実施することは可能である。その際は、前回の実施報告書を基に必要性を十分に検討し、改めて集中的支援実施計画を作成する必要がある。
Q. 広域的支援人材に加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か。
A. 基本的には加算による額(1000単位相当)を支払うことを想定している。加えて、個別の状況によって必要な費用等が異なることから、加算による額を上回る額とすることは差し支えない。
まとめ:算定に向けた準備
集中的支援加算は、支援が困難な強度行動障害児の状態悪化に対し、外部の専門家の力を借りて集中的に対応するための加算です。算定は事業所(児発・放デイ)にとって大きな助けとなりますが、同時に支援の質を向上させる絶好の機会でもあります。
算定を検討する事業所は、以下の点を準備しておくことが重要です。
- 強度行動障害児支援加算確認票に基づき、対象となり得る児童を把握しておく。
- 児童の状態悪化の兆候が見られた際に、速やかに自治体の担当窓口(障害福祉課など)へ相談できる体制を整えておく。
- 広域的支援人材を受け入れ、共同で計画作成や支援見直しを行うための体制(職員間の情報共有、時間の確保)を整備しておく。
公的資料・参考文献
本記事は、以下の公的資料に基づき作成しています。解釈や申請手続きの詳細については、必ず最新の公式情報をご確認の上、管轄の自治体へお問い合わせください。
こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(障害児関係)」(令和6年3月27日)