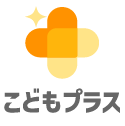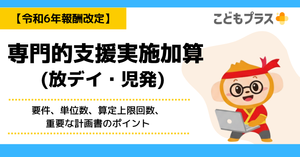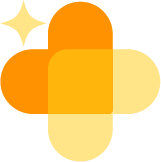専門的支援実施加算と「体制加算」の違い
今回の改定で新設された2つの加算は役割が異なります。
- 専門的支援体制加算(体制) 専門職(PT, OT, STなど)を「配置」していること(体制)を評価する加算です。
- 専門的支援実施加算(実施) 配置した専門職が、個別に計画を立て、専門的な支援を「実施」したこと(行動)を評価する加算です。
この2つの加算は、要件を満たせば両方とも算定(併算定)が可能です。この記事では、後者の「実施加算」について解説します。
専門的支援実施加算の算定要件(誰が・何を)
加算を算定するには、大きく分けて「スタッフ要件」と「実施要件」の2つを満たす必要があります。
【スタッフ要件】配置すべき専門職(理学療法士等)
以下のいずれかの資格・経験を持つスタッフを事業所に1名以上配置する必要があります。(常勤換算の定めはありません)
- 理学療法士(PT)
- 作業療法士(OT)
- 言語聴覚士(ST)
- 心理担当職員(公認心理師、臨床心理士、または心理学を修了した者)
- 視覚障害児支援担当職員
- 保育士(資格取得後、児童福祉事業に5年以上従事した者)
- 児童指導員(任用後、児童福祉事業に5年以上従事した者)
※注意点:これらのスタッフは、児童指導員等加配加算や、専門的支援体制加算の算定対象となっているスタッフと兼務しても構いません。
【実施要件】行うべき支援内容
「専門的支援実施計画」の作成
個別支援計画とは別に、専門職がアセスメントを行い、5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)のうち、特に重点的に支援する領域を定めた「専門的支援実施計画」を作成します。
保護者の同意
作成した「専門的支援実施計画」について、保護者に説明し、文書で同意を得る必要があります。
30分以上の専門的支援の実施
作成した計画に基づき、専門的支援を1回につき30分以上実施します。
支援の形態
支援は「個別支援」が基本ですが、利用児のニーズに応じて「小集団(5名程度まで)」での実施も可能です。
支援記録の作成
支援を実施した都度、児童ごとに「支援日」「支援時間」「支援内容の要点」を記録します。
計画の見直し
実施状況や課題を把握し、定期的に計画を見直します。
専門的支援実施加算の単位数と月間算定上限回数
専門的支援実施加算の単位数は1回あたり150単位ですが、サービスの種別や月の利用日数によって、1人あたりに算定できる「上限回数」が細かく定められています。
月間算定上限回数
お子さま1人あたりの、1ヶ月の算定上限回数は以下の通りです。
【児童発達支援(児発)】
- 月の利用日数が12日未満の場合: 月4回まで
- 月の利用日数が12日以上の場合: 月6回まで
【放課後等デイサービス(放デイ)】
- 月の利用日数が6日未満の場合: 月2回まで
- 月の利用日数が6日以上12日未満の場合: 月4回まで
- 月の利用日数が12日以上の場合: 月6回まで
専門的支援実施加算の計画書と記録のポイント
この加算の算定において、実地指導などで最も重要視されるのが「専門的支援実施計画」と「日々の記録」です。
専門的支援実施計画に記載すべき項目
厚生労働省のQ&A(R6.3.29)によれば、計画書には主に以下の項目を記載することが想定されています。
- 専門職によるアセスメントの結果
- 5領域との関係(特に支援を要する領域)
- 専門的支援によって目指すべき達成目標
- 目標達成のために行う具体的な支援内容
- 支援の実施方法(個別、小集団など)
これらは個別支援計画とは別に作成し、保護者の同意(署名・捺印)を得て保管する必要があります。
日々の支援記録
「支援を行った」という証拠(エビデンス)を残すため、支援の都度、以下の内容を必ず記録します。
- 支援を行った日時
- 支援内容の要点(計画のどの項目に基づき、何分間、何を行ったか)
- 担当した専門職の氏名
専門的支援実施加算 Q&A(厚労省・こども家庭庁)
令和6年度の報酬改定に関するQ&Aから、特に重要なものを抜粋します。
Q1. 児童発達支援管理責任者(児発管)が欠席(欠如)している場合、算定できますか?
-A1. 算定できません。
児発管が欠如している(人員基準を満たしていない)状態では、本加算は算定不可とされています。(R6報酬改定Q&A VOL.4 問1)
Q2. 外部の法人から専門職(PTやOT)を派遣してもらい、支援を行いました。算定できますか?
-A2. 算定できません。
本加算の対象となる専門職は、事業者と「雇用契約」を締結している(または非常勤等で事業所に配置されている)必要があります。外部からの訪問・派遣による支援は対象外です。(R6報酬改定Q&A VOL.3 問9)
Q3. 月の上限回数(例:月6回)は、A事業所とB事業所で合算してカウントしますか?
-A3. いいえ、合算しません。
算定回数の上限は、事業所ごとにカウントします。A事業所で6回、B事業所で6回算定することも制度上は可能です。(R6報酬改定Q&A VOL.5 問4)
Q4. 5年以上の経験を持つ児童指導員が計画を作成・支援しても算定できますか?
-A4. はい、算定できます。
「理学療法士等」には「5年以上児童福祉事業に従事した児童指導員・保育士」も含まれます。これらのスタッフがアセスメント、計画作成、支援(30分以上)、記録の一連の業務を行えば算定対象となります。
専門的支援実施加算の公的な引用・参考文献
本加算の算定根拠や解釈は、以下の公的資料に基づいています。必ず管轄の指定権者(市町村)の最新情報も併せてご確認ください。
こども家庭庁:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)関連
報酬改定の「概要」や、記事で引用されている「Q&A(VOL.1~5など)」
「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)
令和6年度の改定は、この告示の一部を改正する形で行われています。
「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和6年改正版)
さいごに
放課後等デイサービスや児童発達支援の運営は、法令順守と質の高い支援の両立が常に求められます。 全国200教室以上の運営実績を持つこどもプラスでは、長年培ったノウハウに基づき、専門的支援実施加算をはじめとする最新の加算要件の体制構築に対応した実務研修と、安心のサポート体制を提供。適切な加算取得と安定運営を徹底サポートします。
まずは資料をダウンロードして、詳細をご確認ください。資料ダウンロードはこちら