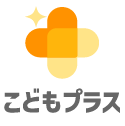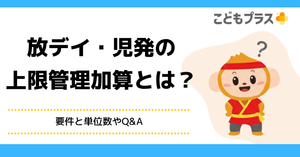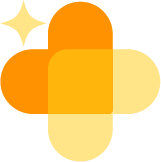上限管理加算の算定要件を理解する
この加算を算定するには、大きく分けて2つの要件をクリアする必要があります。
① 保護者からの「管理申出」があること
大前提として、そのお子さまが(自事業所以外の)複数の障害福祉サービスを利用している必要があります。その上で、保護者から自事業所を「上限額管理事業所」として指定する旨の依頼(申出)を受け、契約を結ぶ必要があります。
② 実際に「負担額の調整」を行うこと
依頼を受けたら、月末に他の利用事業所(併給先)と連携し、各事業所のサービス提供実績と利用者負担額を集約します。その合計額と負担上限月額を照合し、各事業所が請求する最終的な利用者負担額を算出して「利用者負担額上限額管理結果表」を作成・共有する実務が求められます。
算定できない主なケース
- お子さまが自事業所しか利用していない場合
- (1人の児童が複数事業所を使っているのではなく)同一世帯の兄弟が、それぞれ1つの事業所(例:自事業所のみ)に通っている場合
上限管理加算の単位数と具体的な計算方法
上限管理加算の単位数と、それによる収益の計算方法は以下の通りです。
管理を担当するお子さま1人につき、月に1回算定できます。
具体的な計算方法
算定額は「単位数 × 管理を担当する児童数 × 地域単価」で決まります。地域単価は1単位=10円の地域もあれば、11.2円の地域もあります。
<計算例>
地域単価が11.2円の地域(例:東京都23区など)で、3名のお子さまの上限管理を担当した場合
- 150単位 × 3名 = 450単位
- 450単位×11.2円 = 5,040円/月
この金額が、通常の基本報酬や他の加算に加えて事業所の収益となります。
上限管理加算 よくある質問(Q&A)
上限管理加算の算定や実務において、よく寄せられる疑問にお答えします。
Q1. 兄弟が同じ事業所を利用する場合も対象ですか?
-A1. いいえ、対象外です。
上限管理加算は、「1人のお子さまが複数の事業所を」利用する場合に、その負担額を調整する事業所が算定するものです。同一世帯の兄弟が1つの事業所だけを利用する場合、世帯としての負担上限額の調整(合算)は行いますが、本加算の算定はできません。
Q2. 保護者からの「依頼(申出)」はいつ受ければよいですか?
-A2. サービス利用開始時や、他の事業所の併用が決まった時点です。
管理が必要になる前に受けるのが理想です。「利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書」などの書式を用いて、保護者から署名・捺印をもらい、受給者証とともに事業所で保管します。
Q3. 月の途中で管理担当になりました。単位数は日割りですか?
-A3. いいえ、日割りにはなりません。
上限管理加算(150単位/月)は、月の途中で管理依頼を受けた場合でも、その月の調整業務(月末の集計・管理)を実際に行えば、満額の150単位を算定できます。
Q4. 他事業所との連携ミスで、調整に失敗したらどうなりますか?
-A4. 原則、算定できません。
上限管理加算は、適正に「通所利用者負担額合計額の管理を行うこと」が要件です。もし事業所のミスにより保護者から上限額を超えた負担額を徴収してしまった場合などは、加算は算定できず、過誤調整(請求の取り下げ・再請求)が必要になる可能性があります。速やかに保険者(市町村)に相談してください。
公的資料
この加算の根拠や詳細な解釈は、国や自治体が発表する以下の公的資料で確認できます。報酬改定で変更されることもあるため、最新の情報を参照することが重要です。
厚生労働省 告示「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)
厚生労働省 通知(留意事項・Q&A)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(障発0330第12号 平成24年3月30日など)
さいごに
放課後等デイサービスや児童発達支援の運営は、法令順守と質の高い支援の両立が常に求められます。 全国200教室以上の運営実績を持つこどもプラスでは、長年培ったノウハウに基づき、上限管理加算をはじめとする最新の加算要件の体制構築に対応した実務研修と、安心のサポート体制を提供。適切な加算取得と安定運営を徹底サポートします。
まずは資料をダウンロードして、詳細をご確認ください。資料ダウンロードはこちら