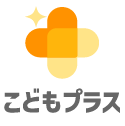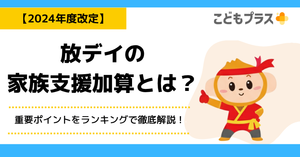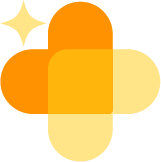家族支援加算の基本概要【第1位】
最重要ポイントは、この加算が「家族との連携」をこれまで以上に評価する制度であるという点です。
これまでの「家庭連携加算(居宅訪問)」と「事業所内相談支援加算(事業所での面談)」が一本化され、支援の選択肢が広がりました。
- 目的: 障がいのある児童を育てる家族(保護者やきょうだい等)の悩みや不安に寄り添い、専門的な相談援助を行うことを評価する加算です。
- 特徴: 事業所だけでなく、ご自宅への訪問やオンラインでの相談も可能となり、家族が利用しやすい形で支援を提供できるよう設計されています。
日々の送迎時の短いやり取りだけでなく、時間を確保してじっくりと家族と向き合うことが、加算という形で評価されるようになったのです。
家族支援加算の支援タイプ:「個別」と「グループ」【第2位】
次に重要なのが、加算の対象となる支援には2つの大きな柱があることです。
ご自身の事業所でどのような支援が可能か、イメージしながらご確認ください。
家族支援加算(Ⅰ):一対一でじっくり向き合う「個別支援」
ご家庭ごとの個別の課題や悩みに深く寄り添うための支援です。支援方法によって単位数が異なります。
- (1) 居宅訪問:スタッフがご自宅に伺い、相談に乗ります。
- (2) 事業所での対面:事業所に来ていただき、個室などで落ち着いて面談します。
- (3) オンライン:テレビ電話などを活用し、遠隔で相談援助を行います。
家族支援加算(Ⅱ):悩みや経験を共有する「グループ支援」
複数の保護者(2人~8人)を集めて、グループ形式で相談援助を行います。同じ立場の保護者同士がつながる貴重な機会を提供できます。
- ペアレントトレーニングの実施
- テーマを決めた保護者座談会や勉強会
- きょうだい児向けのワークショップ
これらの支援をオンラインで行うことも可能です。事業所の特色を活かした企画を立てることで、算定のチャンスが広がります。
家族支援加算の単位数【第3位】
事業運営において単位数は非常に重要です。どの支援がどれだけ評価されるのか、しっかり把握しておきましょう。
特に居宅訪問での支援が最も高く評価されているのがポイントです。
| 加算の種類 | 支援方法 | 単位数 |
| 家族支援加算(Ⅰ) (個別支援) | (1) 居宅を訪問(1時間以上) | 300単位 |
| (1) 居宅を訪問(1時間未満) | 200単位 | |
| (2) 事業所等で対面 | 100単位 | |
| (3) オンライン | 80単位 | |
| 家族支援加算(Ⅱ) (グループ支援) | (1) 対面 | 80単位 |
| (2) オンライン | 60単位 |
家族支援加算の必須ルール【第4位】
加算を確実に算定するためには、定められたルールを守ることが絶対条件です。以下の4点は必ず押さえてください。
計画・同意が必須
支援を行う前に、必ず通所支援計画書に相談援助を行うことを明記し、保護者から同意を得ておく必要があります。送迎時の立ち話のような突発的な相談は対象外です。
原則30分以上
相談援助は1回あたり30分以上行うのが原則です。(※居宅訪問でやむを得ない事情がある場合を除く)
記録を残す
いつ、誰に、どのような相談援助を行ったか、内容の要点を必ず記録してください。この記録が算定の根拠となります。
月4回の回数制限
1人の児童につき、個別支援(Ⅰ)とグループ支援(Ⅱ)を合わせて月に4回まで算定できます。きょうだいで利用されている場合は、それぞれのお子様について月4回まで算定が可能です。
家族支援加算の実務上の重要Q&A【第5位】
最後に、現場で判断に迷いがちな実務上の注意点をご紹介します。これらは公式Q&Aで示されている重要なポイントです。
人員配置に注意!
お子様への支援提供時間中に、職員が家族の相談に乗る場合、その職員は支援単位の基準人員(児童指導員や保育士など)に含めることはできません。
別途、相談担当の職員を配置する必要があります。
モニタリング面談は対象外
個別支援計画の見直しのために行う定期的なモニタリング面談は、児童発達支援管理責任者の本来業務のため、この加算の算定対象にはなりません。
お子様がいなくてもOK 相談援助は、保護者やきょうだいのみが参加し、障がいのあるお子様本人がその場にいない場合でも算定可能です。
まとめ
2024年度からスタートした「家族支援加算」は、事業所が家族に寄り添う姿勢をより強く後押しする制度です。
- 制度の基本(2加算が統合)を理解し、
- 個別支援とグループ支援の2種類があることを知り、
- 支援ごとの単位数を把握し、
- 計画・同意・記録・回数制限のルールを守り、
- 人員配置などの実務上の注意点を押さえる。
これらのポイントを確実に実行することで、算定漏れを防ぎ、事業所の収益向上と支援の質の向上を両立させることができます。ぜひ積極的に活用し、こどもたちだけでなく、その家族全体を支える事業所を目指しましょう。
公式Q&A、参考文献
本記事は、こども家庭庁/厚生労働省の公式Q&A(VOL.1, VOL.2, VOL.4)に基づき作成しています。
法令の解釈や申請は自治体により異なる場合があります。個別の判断や申請については、必ず管轄の自治体へ直接お問い合わせください。
さいごに
放課後等デイサービスや児童発達支援の運営は、法令順守と質の高い支援の両立が常に求められます。
全国200教室以上の運営実績を持つこどもプラスでは、長年培ったノウハウに基づき、家族支援加算をはじめとする最新の加算要件に対応した実務研修と、安心のサポート体制を提供。適切な加算取得と安定運営を徹底サポートします。
まずは資料をダウンロードして、詳細をご確認ください。資料ダウンロードはこちら