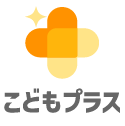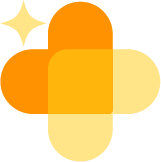放課後等デイサービス経営が厳しく赤字になる主な理由

放課後等デイサービス経営は厳しいと感じる事業者が多く、赤字に陥る背景には、市場環境の変化と知識不足による誤った判断があります。
放課後等デイサービス業界は急成長を遂げている一方で、経営の難しさを訴える声も少なくありません。
実際に赤字経営に陥る事業所には共通した特徴があり、その理由を理解することは成功への第一歩となります。
多くの事業者が直面している課題を知ることで、放課後等デイサービスの赤字を事前に回避する対策を講じることができるでしょう。
市場環境の変化と競争激化
放課後等デイサービス事業所数は近年急激に増加しており、令和5年時点で全国に約20,000カ所を超える施設が存在しています。
この急速な拡大により、利用者の獲得競争が激しくなっています。
特に都市部では事業所が密集し、差別化が困難な状況となっています。
単純に施設を開設しただけでは利用者が集まらず、結果として経営が困窮するケースが増加しています。
「給付費で運営される福祉事業だから安定している」という甘い認識で参入した事業者ほど、現実の厳しさに直面することが多いのです。
給付費と税制に関する誤解
放課後等デイサービス経営が厳しくなる大きな要因の一つが、給付費や税制に対する誤解です。
よくある間違いとして以下のようなものがあります。
- 「給付費で賄われるから景気に左右されず安定している」
- 「非課税で税制優遇が受けられる」
- 「利用者が来れば自動的に収入が入る」
実際には、給付費は単位制で計算され、利用者数や職員配置、提供サービスによって大きく変動します。
また、非課税となるのは消費税のみで、法人税は通常通り課税されます。これらの誤解が、想定外の収支悪化を招く原因となっています。
本来取得できる加算の見落とし
多くの事業所が見落としがちなのが、本来取得できるはずの加算を逃していることです。
特に「児童指導員等加配加算」は比較的取得しやすい加算の一つですが、以下のような理由で取得できていない事業所があります。
- 加配加算の効果を知らず、規定人数で運営を続けている
- 給与負担を恐れて有資格者の採用を避けている
- 一般職員のスキルアップ機会を提供していない
「児童指導員等」には、強度行動障害支援者養成研修や重度訪問介護従業者養成研修の修了者も含まれます。
これらの研修は10〜20時間程度で修了でき、一般職員でも「児童指導員等」として123単位の加算を取得することが可能です。
放課後等デイサービス経営は厳しい状況にありますが、赤字に陥る理由の多くは正しい知識と戦略の不足にあり、これらを解決することで安定した運営が可能になります。
次に、放課後等デイサービス経営を厳しくし赤字につながる報酬改定のリスクと、その対策について詳しく見ていきましょう。
放課後等デイサービス経営を厳しくし赤字を招く報酬改定への対策

放課後等デイサービス経営は厳しい状況に陥りやすく、赤字の要因として3年に一度行われる報酬改定の影響があります。
報酬改定は、より効果的なサービス提供を目的として実施されますが、事業所運営には大きな影響を与えます。
これまで取得できていた加算が取得できなくなったり、基本報酬が変更されたりすることで、売上が大幅に減少し放課後等デイサービスの赤字経営につながるリスクがあります。
令和3年の報酬改定を例に、具体的な変化とその対策を解説します。
令和3年報酬改定の影響
令和3年の報酬改定では、事業所の区分制度が大きく変更されました。改定前後の変化を比較してみましょう。
改定前の制度
事業所は指標該当児の受け入れ割合により二つに区分されていました:
区分1(指標該当児50%以上)
- 基本報酬(平日):660単位(3時間以上)、649単位(3時間未満)
- 児童指導員等加配加算Ⅰ:理学療法士等209単位、児童指導員等155単位
区分2(指標該当児50%未満)
- 基本報酬(平日):612単位(3時間以上)、599単位(3時間未満)
- 児童指導員等加配加算Ⅰ・Ⅱの重複取得が可能
改定後の制度
区分制度が廃止され、統一された基準となりました:
- 基本報酬(平日):604単位
- 児童指導員等加配加算:理学療法士等187単位、児童指導員等123単位
一見すると単位数が減少したように見えますが、新たに以下の加算が創設されました:
新設された加算
- 専門的支援加算:187単位(理学療法士、作業療法士等の配置)
- 個別サポート加算Ⅰ:100単位(ケアニーズが高い児童への支援)
- 個別サポート加算Ⅱ:125単位(要保護・要支援児童の受け入れ)
報酬改定で見える行政の方向性
令和3年の改定から読み取れる行政の方向性は明確です。「個別」かつ「専門的」な支援により重点を置く方針が示されています。
この流れを理解し、事前に準備することが重要です。
(参照:厚生労働省「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」)
こどもプラスでは、報酬改定に対応するため、これまでの改定の軌跡を辿り、行政が示す方向性を分析しています。
令和3年の報酬改定では、「専門性」や「個別対応」の力をより問われるようになりました。
また、こどもプラスでは「現場にいるからこそわかること」「実際に運営しなければわからないこと」を「要望書」として厚生労働大臣に提出した実績があります。



令和3年6月1日付で要望書を作成し、元・厚生労働大臣政務官の大隈和英様、参議院議員の自見英子様に内容をご説明の上、書面をお渡ししました。
コロナ禍での柔軟な対応や人員配置要件の緩和、処遇改善額の見直しなど全9項目の内容を記述し、現場目線での提言を行いました。
今後の報酬改定でも、以下のような要素がより重視される可能性があります。
- 専門職員による質の高いサービス提供
- 一人ひとりのこどもに応じた個別支援計画の実践
- 家族や地域との連携強化
- 将来の自立に向けた支援内容の充実
報酬改定リスクへの対策
放課後等デイサービス経営が厳しい状況に陥らないためには、報酬改定を見据えた戦略的な準備が必要です。
専門性の向上
理学療法士や作業療法士などの専門職員の確保は容易ではありませんが、以下のような取り組みで専門性を高めることができます。
- ・職員の資格取得支援制度の導入
- ・外部専門家との連携体制の構築
- ・専門的な研修プログラムの実施
個別支援の充実
個別サポート加算の取得を目指し、以下の取り組みを推進します。
- ・アセスメント能力の向上
- ・個別支援計画の質的向上
- ・保護者との密な連携
先進的なサービスの導入
将来の制度変更を見据え、以下のようなサービスを早期に導入することが有効です。
- ・言語聴覚療法
- ・ビジョントレーニング
- ・プログラミング教育
- ・就労支援・自立支援プログラム
放課後等デイサービス経営は厳しい環境変化にさらされ赤字のリスクがありますが、報酬改定の方向性を理解し、専門性と個別支援を重視した運営により安定した経営が実現できます。
続いて、放課後等デイサービス経営を厳しくし赤字に導く経費管理の落とし穴について解説します。
放課後等デイサービス経営が厳しく赤字になる経費管理の落とし穴

放課後等デイサービス経営は厳しい状況に陥りやすく、赤字の大きな要因として適切な経費管理ができていないことがあげられます。
経営を安定させるためには、発生する経費を正しく理解し、「抑えるべき経費」と「かけるべき経費」を明確に区別する必要があります。
特に人件費は経営を大きく左右する要素であり、適切なコントロールが不可欠です。黒字施設の人件費率は67%であるのに対し、赤字施設では93.7%となっており、人件費管理の重要性が明確に示されています。
(参照:独立行政法人福祉医療機構「2018年度 児童系障害福祉サービスの経営状況について」)
放課後等デイサービスで発生する経費一覧
まず、放課後等デイサービス運営で発生する主な経費を整理しましょう。
運営に必要な経常経費
- ・人件費(給与・役員報酬・賞与・法定福利費)
- ・賃料(家賃・駐車場代)
- ・FCロイヤリティ(FC加盟の場合)
- ・車両関連費用(リース代・保険・ガソリン代)
- ・専門家費用(税理士・社労士顧問料)
- ・各種保険料
- ・消耗品費
- ・通信費
- ・水道光熱費
開設時に必要な初期費用
- ・テナントの敷金・礼金
- ・内装工事費
- ・備品・設備購入費
- ・広告宣伝費
これらの経費を適切に管理することで、利益を最大化し、安定した経営基盤を築くことができます。
抑えるべき経費の徹底管理
小口現金の管理
教室に置く小口現金は、交通費や急な備品購入に必要ですが、管理が甘くなりがちな経費でもあります。
「上限まで使わなければ損」という意識が働き、不要な支出につながることがあります。
明確な使用基準を設け、定期的な見直しを行うことで無駄な支出を防げます。
レシートの保管と月次での精算を徹底し、必要性の低い支出を排除しましょう。
残業代の削減
人件費の中でも特に注意が必要なのが残業代です。
働き方改革により時間外労働の上限規制が設けられており、長時間労働の是正が求められています。
(参照:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」)
放課後等デイサービスでは「こどものため」という理由で長時間労働が常態化しやすい環境にあります。
しかし、適切な業務分担と効率化により残業を削減することは十分可能です。
残業削減のポイント
- ・業務の標準化と効率化
- ・適切な人員配置の検討
- ・業務分担の見直し
- ・ITツールの活用による事務作業の効率化
かけるべき経費への投資
一方で、以下の分野には積極的に投資することで、長期的な収益向上につながります。
集客関連費用
利用者が集まらなければ事業は成り立ちません。以下の集客活動には適切な予算を確保しましょう。
- ・体験会の開催費用
- ・地域イベントへの参加費
- ・広告宣伝費(効果測定を前提として)
- ・ホームページの充実
職員のスキルアップ費用
職員の専門性向上は、加算取得や利用者満足度向上に直結します。
- ・資格取得支援費用
- ・研修参加費
- ・外部講師招聘費
- ・専門書籍や教材費
設備・環境改善費用
安全で魅力的な環境づくりは利用者確保の基本です。
- ・安全設備の充実
- ・療育用具の購入
- ・環境整備費用
人件費率の目標設定と管理
前述の調査結果を参考に、段階的な人件費率の改善を目指しましょう。
| 段階 | 人件費率目標 | 状況 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 70%以下 | 赤字脱却 |
| 第2段階 | 60%以下 | 安定経営 |
| 第3段階 | 50%以下 | 拡大投資可能 |
| 最終目標 | 30%台 | 多店舗展開可能 |
この目標を達成するためには、売上向上と経費管理の両面からのアプローチが必要です。売上を急に増やすことは困難ですが、段階的な利用者増加と効率的な運営により実現可能です。
効率的な人材採用戦略
人件費を抑えながら質の高い職員を確保するための工夫も重要です。
採用コストの削減
- ・ハローワークの活用(無料)
- ・求人検索エンジンの効果的活用
- ・既存職員からの紹介制度
- ・地域の養成校との連携
職員定着率の向上
新規採用よりも既存職員の定着率向上の方がコスト効率が良いことが多いです:
- ・適切な労働環境の整備
- ・キャリアアップ支援
- ・職員間のコミュニケーション促進
- ・適正な評価制度の導入
放課後等デイサービス経営は厳しい環境でも、適切な経費管理により人件費率を抑え、必要な分野への投資を行うことで赤字を回避し収益性の高い運営が実現できます。
最後に、放課後等デイサービス経営を厳しい状況から脱却するためのFC加盟のメリットについて解説します。
放課後等デイサービス経営の厳しさと赤字を解決するFC加盟の優位性

放課後等デイサービス経営は厳しい環境にあり赤字リスクも高まっていますが、経験豊富なFC本部のサポートにより、多くのリスクを回避し安定した運営を実現できます。
独立開業では習得困難な専門知識や運営ノウハウを、FC加盟により効率的に身につけることができます。
特に、給付費制度の理解、報酬改定への対応、効果的な経費管理などの複雑な要素を、実績のあるFC本部がサポートすることで、経営の安定性が大幅に向上します。
FC加盟による知識とノウハウの獲得
給付費制度の完全理解
放課後等デイサービスの給付費は単位制で計算され、以下の要素で決定されます:
基本的な計算式 「一日児童一人あたりの単位数」×「地域単価(10円〜)」×「利用人数」
定員10名以下の教室での基本報酬単位は以下の通りです:
- 平日:604単位
- 学校休業日:721単位
これに各種加算を組み合わせることで収益を最大化します。例えば、児童指導員等加配加算(123単位)と送迎加算(往復108単位)を取得した場合:
- 平日:604+123+108=835単位(地域単価10円なら8,350円/人)
- 学校休業日:721+123+108=952単位(同9,520円/人)
FC本部では、これらの制度を熟知したスタッフが最適な加算取得方法を指導します。
報酬改定への戦略的対応
FC本部の強みの一つは、報酬改定の動向を早期に察知し、対応策を準備できることです。
こどもプラスの対応実績
- ・厚生労働大臣への要望書提出(令和3年6月)
- ・現場の声を反映した制度改善提案
- ・次期改定を見据えたサービス開発
現在求められる「専門性」と「個別対応」に対応したコンテンツとして以下を提供。
- ・言語聴覚療法「ことばの教室」
- ・ビジョントレーニング
- ・プログラミング・ドローン教育
- ・就労支援・自立支援プログラム
経営安定化のための総合支援
開業前の充実したサポート
FC加盟により、開業前から以下の支援を受けられます。
立地・設計支援
- ・最適な立地選定アドバイス
- ・効率的なレイアウト設計
- ・安全基準に適合した設備計画
行政手続きサポート
- ・指定申請書類の作成支援
- ・自治体との折衝サポート
- ・必要な資格・研修の案内
職員採用・研修
- ・効果的な求人方法の指導
- ・面接・選考のサポート
- ・開業前職員研修の実施
開業後の継続的なサポート体制
運営管理の最適化 FC本部のスーパーバイザー(SV)による定期的な巡回指導により、以下の支援を継続的に受けられます。
- ・利用者対応の改善指導
- ・職員のスキルアップ支援
- ・加算取得のための具体的アドバイス
- ・経費管理の最適化提案
集客・マーケティング支援
- ・実績のある集客手法の共有
- ・地域に応じたマーケティング戦略
- ・体験会・説明会の開催支援
- ・保護者満足度向上のための取り組み
リスク回避と収益性向上
人件費管理のノウハウ共有
独立開業では困難な人件費の最適化を、FC本部の豊富な経験により実現できます。
段階的な人件費率改善
- 開業初期:安定した職員確保(人件費率70%以下目標)
- 成長期:効率化による改善(同60%以下目標)
- 成熟期:多店舗展開準備(同50%以下目標)
- 拡大期:スケールメリット活用(同30%台目標)
継続的な収益向上策
実費事業の導入支援 給付費以外の収入源として、以下の実費事業を展開できます:
- ・専門的な個別指導
- ・長期休暇中の特別プログラム
- ・保護者向けセミナー・相談事業
多店舗展開のサポート 1店舗目が軌道に乗った後の展開戦略として:
- ・年齢別特化型教室の開設
- ・地域ニーズに応じたサービス分化
- ・効率的な管理体制の構築
FC加盟の具体的メリット
初期投資の最適化
- ・実績に基づく適正な投資額の設定
- ・無駄のない設備・備品の選定
- ・開業時期の最適化
運営効率の向上
- ・標準化された業務フローの導入
- ・効果的な記録・報告システム
- ・職員教育プログラムの活用
リスクの最小化
- ・法令遵守の徹底指導
- ・トラブル対応のノウハウ共有
- ・経営指標のモニタリング支援
放課後等デイサービス経営は厳しい環境にあり赤字のリスクもありますが、FC加盟により専門知識、運営ノウハウ、継続的サポートを得ることで、安定した収益性の高い事業運営が実現できます。適切なパートナー選びが成功への最短距離となるでしょう。